イベント / EVENT
大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」
2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、大学等においては遠隔講義に関する検討がなされてきました。国立情報学研究所ならびに大学の情報環境のあり方検討会では、大学等における遠隔授業や教育DX等に関する情報を共有することを目的に、2020年3月末より週1回から隔週のペースで、大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」(「4月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」から名称変更)を継続的に開催しています。
大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」
【第90回】 大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」(7/11 オンライン開催)
開催日時 2025年7月11日(金)10:30 -
共催 国立情報学研究所 大学の情報環境のあり方検討会
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
本シンポジウムは、下記申込みフォームよりお申込みをお願いします。
お申込み
【第90回】申込みフォームはこちら
※申込登録の後、Web会議システム、質問用 Slackへの接続先情報等を自動返信メールでお送り致しております。万が一、dc-sympo[at]nii.ac.jp からのメールが届かない場合は、「大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム(教育機関DXシンポ)」運営担当までご連絡を頂けますようお願いいたします。
プログラム
- 10:30 はじめに
1.「はじめに」
喜連川 優 情報・システム研究機構長 - 10:32 間接業務の経験から
2.「大学評価・情報基盤・教養教育の経験から見た大学」
喜多 一 大学ICT推進協議会、京都大学 名誉教授
概要講演者は京都大学助手、東京工業大学助教授として教育研究活動に従事したのち、2000年から大学評価・学位授与機構(現在の大学改革支援・学位授与機構)で試行段階の大学の第三者評価を担当した、2003年からは京都大学学術情報メディアセンターで教育用の情報システムの企画運用を担当し、さらに2013年から2025年まで同大学国際高等教育院で教養教育を担当した。
とくに2013年から2016年までは同院、副教育院長として教養教育の改革に携わった。その後、2016年から2021年までは同大学情報環境機構長として大学の情報基盤全体を統括し、2020年度の全面オンライン授業実施については授業のオンライン実施を支援した。2023年度からは大学ICT推進協議会の事務局長代行を兼務し、2025年度から非常勤の事務局長として大学の情報基盤について大学間連携の促進に従事している。
本講演では、これら間接業務の経験から大学について論じる。 - 10:57 海外事例・IR
3.「IRにできること、できないこと」
本田 寛輔 大学IRと学修成果コンサルティング 創設者・主任分析官
概要大学の機関情報を集約し、意思決定や継続的な改善を支援するInstitutional Research(IR)業務の導入が謳われて10年以上過ぎました。現在の状況は国立大学と私立大学で異なるようです。米国で大学運営の博士号を取得し、実務でもIRと学修成果の測定に10数年関わってきた経験から、米国のIR事情を発表します。項目は1.大学類型によるIR業務の違い、2.IRデータの活用、3.意思決定の複雑性、4.最近の米国高等教育の動向で、日本のIR事情を振り返る写し鏡として参考になればと願います。 - 11:22 大学DX
4.「東京大学における生成AIの業務利活用に向けて」
阿部 仁志 東京大学 本部DX推進課業務改革チーム・副課長
廣本 和哉 東京大学 本部情報支援課業務支援チーム・係長
概要東京大学における生成AIの業務利活用に向けた検証のうち、東大RAG(AISearch)とMicrosoft365Copilotの検証状況について報告する。 - 11:47 生成AI
5.「LLMの学習メカニズムの解明」
磯沼 大 国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター / 東北大学言語AI研究センター 特任助教
概要大規模言語モデルはいつ何を学習したことで高い知的能力を獲得しているだろうか。学習データの組み合わせや順序を試行錯誤することで、知的能力獲得に重要なデータや最適な学習順序を明らかにできるかもしれないが、大規模言語モデルの学習データは膨大なため現実にはそうした試行錯誤は困難である。本研究では逆学習といった技術を用いることで、大規模言語モデルの学習メカニズムを解明する取り組みについて紹介する。これらの取り組みにより、将来的に人の知的能力獲得プロセスの理解につながることを目指している。 - 12:12
6.「ディスカッション」 - 12:32
おわりに
喜連川 優 情報・システム研究機構長
ChatGPT利用経験アンケート調査 ご協力のお願い
当シンポジウムで取り上げたChatGPTについて、経験談を集約することでその能力と限界を明らかにすることを目的としたアンケート調査を実施いたします。
皆様のChatGPT3.5/4.0を使った経験談のご提供をよろしくお願い申し上げます。
なお、ご提供いただいた内容は、現状の把握ならびに今後の研究のために利用させていただきます。
https://nii.qualtrics.com/jfe/form/SV_39Gc0qluKEvgsRg
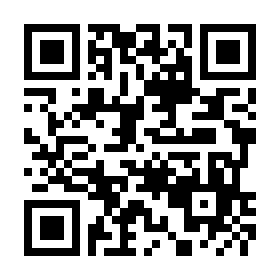 スマートフォンでお答えの場合は
スマートフォンでお答えの場合は
こちらのQRコードから
お問い合わせ
国立情報学研究所
大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」」運営担当
dc-sympo[at]nii.ac.jp
参考情報
- これまで開催した本シンポジウムの講演資料と映像が検索できます
教育機関DXシンポアーカイブズ - これまで開催した本シンポジウムのプログラム一覧です
「教育機関DXシンポ」過去開催一覧 - バーチャルイベントを開催する教育研究機関を支援します
学校のバーチャルイベントのための「サイバー大講堂」 - 各種オンライン会議ツールのチェックリストです
「オンライン会議サービス用チェックリスト一覧」(学認クラウド導入支援サービス) - 通信量に配慮した授業の実施・設計手法のご案内です
「データダイエットへの協力のお願い:遠隔授業を主催される先生方へ」(2020/05/07)
「情報学最前線」 平成28年度 特別会 Q&A 平成28年度 第6回 Q&A 平成28年度 第5回 Q&A 平成28年度 第4回 Q&A 平成28年度 第3回 Q&A 平成28年度 第2回 Q&A 平成28年度 第1回 Q&A 平成27年度
「情報学最前線」 平成27年度 第6回 Q&A 平成27年度 第4回 Q&A 平成27年度 第3回 Q&A 平成27年度 第2回 Q&A 平成27年度 第1回 Q&A 平成26年度
「未来を紡ぐ情報学」 平成26年度 第8回 Q&A 平成26年度 第7回 Q&A 平成26年度 第6回 Q&A 平成26年度 第5回 Q&A 平成26年度 第4回 Q&A 平成26年度 第2回 Q&A 平成26年度 第1回 Q&A 平成25年度
「未来を紡ぐ情報学」 平成25年度 第8回 Q&A 平成25年度 第7回 Q&A 平成25年度 第6回 Q&A 平成25年度 第5回 Q&A 平成25年度 第4回 Q&A 平成25年度 第3回 Q&A 平成25年度 第2回 Q&A 平成25年度 第1回 Q&A 平成24年度
「人と社会をつなぐ情報学」 平成24年度 第8回 Q&A 平成24年度 第7回 Q&A 平成24年度 第3回 Q&A 平成24年度 第1回 Q&A 平成23年度 平成23年度 第8回 Q&A 平成23年度 第7回 Q&A 平成23年度 第6回 Q&A 平成23年度 第5回 Q&A 平成23年度 第4回 Q&A 平成23年度 第3回 Q&A 平成23年度 第2回 Q&A 平成23年度 第1回 Q&A 平成22年度 平成22年度 第8回 Q&A 平成22年度 第7回 Q&A 平成22年度 第6回 Q&A 平成22年度 第5回 Q&A 平成22年度 第4回 Q&A 平成22年度 第3回 Q&A 平成22年度 第2回 Q&A 平成22年度 第1回 Q&A 平成21年度 平成21年度 第8回 Q&A 平成21年度 第7回 Q&A 平成21年度 第6回 Q&A 平成21年度 第5回 Q&A 平成21年度 第4回 Q&A 平成21年度 第3回 Q&A 平成21年度 第2回 Q&A 平成21年度 第1回 Q&A 平成20年度 平成20年度 第8回 Q&A 平成20年度 第7回 Q&A 平成20年度 第6回 Q&A 平成20年度 第5回 Q&A 平成20年度 第4回 Q&A 平成20年度 第3回 Q&A 平成20年度 第2回 Q&A 平成20年度 第1回 Q&A 平成19年度 平成19年度 第8回 Q&A 平成19年度 第7回 Q&A 平成19年度 第5回 Q&A 平成19年度 第2回 Q&A 平成19年度 第1回 Q&A 平成18年度 平成18年度 第8回 Q&A 平成18年度 第7回 Q&A 平成18年度 第5回 Q&A 平成18年度 第3回 Q&A 平成17年度 平成16年度 平成15年度 市民講座アーカイブ


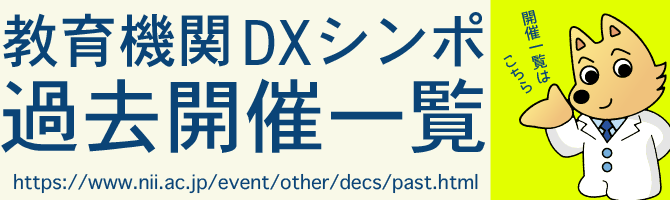
 国立情報学研究所
国立情報学研究所 国立情報学研究所 2025年度 概要
国立情報学研究所 2025年度 概要 NII Today No.104
NII Today No.104 SINETStream 事例紹介:トレーラー型動物施設 [徳島大学 バイオイノベーション研究所]
SINETStream 事例紹介:トレーラー型動物施設 [徳島大学 バイオイノベーション研究所] ウェブサイト「軽井沢土曜懇話会アーカイブス」を公開
ウェブサイト「軽井沢土曜懇話会アーカイブス」を公開 情報研シリーズ これからの「ソフトウェアづくり」との向き合い方
情報研シリーズ これからの「ソフトウェアづくり」との向き合い方 学術研究プラットフォーム紹介動画
学術研究プラットフォーム紹介動画 教育機関DXシンポ
教育機関DXシンポ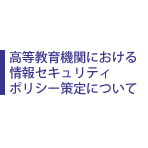 高等教育機関におけるセキュリティポリシー
高等教育機関におけるセキュリティポリシー 情報・システム研究機構におけるLGBTQを尊重する基本理念
情報・システム研究機構におけるLGBTQを尊重する基本理念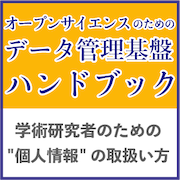 オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック
オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック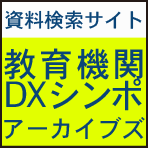 教育機関DXシンポ
教育機関DXシンポ コンピュータサイエンスパーク
コンピュータサイエンスパーク
