イベント / EVENT
平成28年度 特別会 Q&A
特別回 2017年3月1日(水)
ナノサイズの「揺れ」がもたらす新分野
山口 浩司 (NTT物性科学基礎研究所 上席特別研究員)
講演当日に頂いたご質問への回答(全19件)
※回答が可能な質問のみ掲載しています。
10-17mだと十分に量子的な視野ではないでしょうか?
はい。そのとおりです。ただし、私たちの検出方法では、まだ10-15m程度なので、あと二桁程度改善が必要です。
電子デバイスと比較しての、フォノンデバイスの利点はなんでしょうか?
環境の変化に強いと考えられています。例えば、一般に半導体デバイスは温度変化に対して敏感に特性が変化しますが、機械構造の場合はそれほど大きく変化しません。このため、例えば500度でも動作するスイッチなどが提案されています。
フォノンの質量などはどのような値(どのように計算する)のでしょうか?
一般に、素励起の質量は運動量とエネルギーの関係(分散関係と呼ばれます)から与えられます。我々の板バネの場合には、構造の厚さや材料の密度、ヤング率によって決まり、例えば厚さが1ミクロンのシリコンの場合、10-29 グラムという値になります。これは電子の質量と同じ程度の値です。
古典力学で、「空洞共鳴」と呼ばれる物理現象もフォノンによって(あるいはフォノンという概念を使用して)説明できるのでしょうか?
我々が用いている板バネ構造の場合には結晶材料が伸び縮みをしますが、空洞共鳴の場合には気体が伸び縮みします。このように媒質は異なりますが、マクロな古典論の近似ではどちらも同じ方程式で記述できます。一方、フォノンという量子力学的な領域に入ると、媒質のミクロな性質が重要になってきます。板バネ構造の場合には規則正しい単結晶によって媒質が構成されていますが、空洞共鳴の場合は常に分子が飛びまわている気体となっており、規則正しい構造をしていないのみならず、時間とともに構造が変化しています。このような媒質はミクロには連続的な弾性体とはみなされないため、量子力学的なフォノンとしての性質は持ちません。
フォノンの重要性の説明を聞くと、量子性をニュートン力学の分野へ適用できるかを検証しようとしているように思えます。素人考えでは、まず熱力学への適用を検証すべきように思えるのですが、それは既に行われているのでしょうか?
熱力学を量子力学の枠組みで扱うことは、量子力学が作られた段階ですでに行われています。むしろ、古典的な熱力学からの予言(例えばデュロン=プティの法則など)が低温では成立しないことの発見が、量子力学が生まれるきっかけになったといえます。
原子力間顕微鏡に使用されているものも、フォノンデバイスなのでしょうか?その他にも、実際にフォノンデバイスが使用されているものがあれば紹介していただきたいです。
原子間力顕微鏡にはコンタクトモードとタッピングモード、さらにはノンコンタクトモードがあります。後者の2つはカンチレバーを振動させて用いています。このようにカンチレバーが振動している状態は、多くのフォノンが励起されている状態と考えることができるので、フォノンを用いたデバイスであるということができます。ただし、フォノンの量子的な性質を用いているわけではないので、一般にはフォノンデバイスとは呼ばれることはなく、MEMSなどと同様のマイクロメカニカル素子と呼ぶ方が適切かと思います。
原子核10-14m以下の10-17mの振動を検出できることをどのように証明し、キャリブレーションするのでしょうか?
大変鋭い質問です。キャリブレーションには熱による揺れを用います。熱力学の等分配法則によると、どのような力学系も熱によって揺れており、この大きさは温度と質量によって決まります。これを用いて、計測された熱振動の大きさをキャリブレーションします。
フォノンを使用した量子コンピューター(イジングマシン)は可能でしょうか?
簡単ではありませんが、可能性は今後検討していきたいと考えています。
今回ご説明いただいたフォノンデバイスは、一次元の振動子ですが、たとえばねじれを利用した(スピン?)事例はありえるでしょうか?
ねじれ振動モードでは、一般にエネルギー損失が小さいため、鋭い共振の振動子が作られています。磁気センサーとしての応用も研究されています。
フォノンのカプリング状態を量子として扱うことは可能でしょうか?その場合、観測の問題は当てはまるのでしょうか?(観測の問題があてはまらないとすると、本質的な違いがあるのでしょうか?)
2つの振動子におけるフォノンの重ね合わせ状態に対する量子力学的な観測がどのようになるか、という御質問かと推測します。量子力学の原理はすべての物理系において成立しているはずのもので、フォノンの重ね合わせ状態に対しても、成立すると考えられています。
フォノンは「シュレディンガー方程式に従うような量子学的存在」なのか、「量子論的なアナロジーとして考えることができる粒子的存在」のどちらなのでしょうか?
前者かと思います。アナロジーではなく、本当に量子力学的な素励起と考えて良いと思います。
フォノンの場合に「確率的解決」がどのような状況に対応するのか、もう少し詳しく説明して頂けますでしょうか。
量子力学における「確率解釈」についてのご質問でしょうか。フォノンの状態に関しても、やはり理論が予言できることは確率のみということになります。従って、例えば2つの振動子が存在し、そのフォノンが均等な重ね合わせ状態にある場合には、それぞれにフォノンが観測される確率は50%ずつ、ということになります。
実存性と非実存性についてですが、1/2の確率で実存性と非実存性が存在すると言えるが、例えば1/2の存在確立でない(1/4、1/8、、、など)場合、存在することはあり得るのでしょうか?
例として2つの可能性が50%ずつの場合を示しましたが、例えば4つの可能性が25%ずつという場合もあり得ます。
フォノンによるマネジメントができた場合に、何か新しいデバイスが登場するのでしょうか?
フォノンは固体中で熱伝導をつかさどっているため、例えば熱のスイッチができれば、放熱や蓄熱を自在に制御できる装置ができるかもしれません。
微小変位の検出技術は、重力波の検出にも使われていると推測するのですが、互いに技術の交流はあるのでしょうか?
重力波検出で使われているものと原理的に同じ素子を用いて、このような微小振動子の振動検出を行っている例も多くあります。理論研究においては、基本的に同じ方程式で記述できるため、多くの概念が両方の計に対してあてはめられています。
フォノンの運動と、音が空気を伝わることとはどのように関係するのでしょうか?
我々が用いている板バネ構造の場合には結晶材料が伸び縮みをしますが、音の伝搬の場合には気体が伸び縮みします。このように媒質は異なりますが、マクロな古典論の近似では類似した方程式で記述できます。一方、フォノンという量子力学的な領域に入ると、媒質のミクロな性質が重要になってきます。板バネ構造の場合には規則正しい単結晶によって媒質が構成されていますが、空気中の音の伝搬の場合は常に分子が飛びまわている気体となっており、規則正しい構造をしていないのみならず、時間とともに構造が変化しています。このような媒質はミクロには連続的な弾性体とはみなされないため、量子力学的なフォノンとしての性質は持ちません。
量子力学的現象の観測においての大敵である観測ノイズの排除はどのような技術で行っているのでしょうか?
原理的に最後まで残るノイズは熱によるランダムな振動です。これを排除するために、まずは測定試料の温度を下げます。これでも十分でない場合には、レーザー冷却の手法を用います。
E=hν のような波長とエネルギーの関係はあるのでしょうか?
あります。この関係は電子や光子のみならず、フォノンや、あらゆる素励起、素粒子に対しても成り立つ普遍的な関係です。
メカニカル振動子により、量子コンピューターの種のデコヒーレンスである、振動デコヒーレンスに耐えられる量子ビットの実現の可能性はありますでしょうか?
現在、メカニカル振動子のQ値(コヒーレンスの良さ)は100万以上のものが得られており、それを用いると小さなデコヒーレンスを持つ量子系が作れる可能性があります。ただし、量子ビットとしては用いることができないため、量子ビット間の情報変換素子などへの応用が検討されています。
「情報学最前線」 平成28年度 特別会 Q&A 平成28年度 第6回 Q&A 平成28年度 第5回 Q&A 平成28年度 第4回 Q&A 平成28年度 第3回 Q&A 平成28年度 第2回 Q&A 平成28年度 第1回 Q&A 平成27年度
「情報学最前線」 平成27年度 第6回 Q&A 平成27年度 第4回 Q&A 平成27年度 第3回 Q&A 平成27年度 第2回 Q&A 平成27年度 第1回 Q&A 平成26年度
「未来を紡ぐ情報学」 平成26年度 第8回 Q&A 平成26年度 第7回 Q&A 平成26年度 第6回 Q&A 平成26年度 第5回 Q&A 平成26年度 第4回 Q&A 平成26年度 第2回 Q&A 平成26年度 第1回 Q&A 平成25年度
「未来を紡ぐ情報学」 平成25年度 第8回 Q&A 平成25年度 第7回 Q&A 平成25年度 第6回 Q&A 平成25年度 第5回 Q&A 平成25年度 第4回 Q&A 平成25年度 第3回 Q&A 平成25年度 第2回 Q&A 平成25年度 第1回 Q&A 平成24年度
「人と社会をつなぐ情報学」 平成24年度 第8回 Q&A 平成24年度 第7回 Q&A 平成24年度 第3回 Q&A 平成24年度 第1回 Q&A 平成23年度 平成23年度 第8回 Q&A 平成23年度 第7回 Q&A 平成23年度 第6回 Q&A 平成23年度 第5回 Q&A 平成23年度 第4回 Q&A 平成23年度 第3回 Q&A 平成23年度 第2回 Q&A 平成23年度 第1回 Q&A 平成22年度 平成22年度 第8回 Q&A 平成22年度 第7回 Q&A 平成22年度 第6回 Q&A 平成22年度 第5回 Q&A 平成22年度 第4回 Q&A 平成22年度 第3回 Q&A 平成22年度 第2回 Q&A 平成22年度 第1回 Q&A 平成21年度 平成21年度 第8回 Q&A 平成21年度 第7回 Q&A 平成21年度 第6回 Q&A 平成21年度 第5回 Q&A 平成21年度 第4回 Q&A 平成21年度 第3回 Q&A 平成21年度 第2回 Q&A 平成21年度 第1回 Q&A 平成20年度 平成20年度 第8回 Q&A 平成20年度 第7回 Q&A 平成20年度 第6回 Q&A 平成20年度 第5回 Q&A 平成20年度 第4回 Q&A 平成20年度 第3回 Q&A 平成20年度 第2回 Q&A 平成20年度 第1回 Q&A 平成19年度 平成19年度 第8回 Q&A 平成19年度 第7回 Q&A 平成19年度 第5回 Q&A 平成19年度 第2回 Q&A 平成19年度 第1回 Q&A 平成18年度 平成18年度 第8回 Q&A 平成18年度 第7回 Q&A 平成18年度 第5回 Q&A 平成18年度 第3回 Q&A 平成17年度 平成16年度 平成15年度 市民講座アーカイブ
注目コンテンツ / SPECIAL
 NIIサービスニュース
NIIサービスニュース
 国立情報学研究所
国立情報学研究所2025年度 要覧
 国立情報学研究所 2025年度 概要
国立情報学研究所 2025年度 概要
 NII Today No.104
NII Today No.104
 SINETStream 事例紹介:トレーラー型動物施設 [徳島大学 バイオイノベーション研究所]
SINETStream 事例紹介:トレーラー型動物施設 [徳島大学 バイオイノベーション研究所]
 ウェブサイト「軽井沢土曜懇話会アーカイブス」を公開
ウェブサイト「軽井沢土曜懇話会アーカイブス」を公開
 情報研シリーズ これからの「ソフトウェアづくり」との向き合い方
情報研シリーズ これからの「ソフトウェアづくり」との向き合い方
 学術研究プラットフォーム紹介動画
学術研究プラットフォーム紹介動画
 教育機関DXシンポ
教育機関DXシンポ
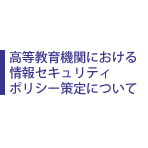 高等教育機関におけるセキュリティポリシー
高等教育機関におけるセキュリティポリシー
 情報・システム研究機構におけるLGBTQを尊重する基本理念
情報・システム研究機構におけるLGBTQを尊重する基本理念
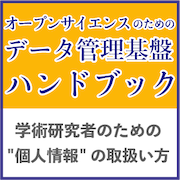 オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック
オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック
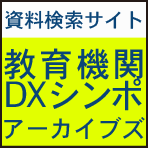 教育機関DXシンポ
教育機関DXシンポアーカイブス
 コンピュータサイエンスパーク
コンピュータサイエンスパーク


