イベント / EVENT
2024年度 第2回 リポート
イベント リポート:「量子コンピュータとは何か? ― 情報学と最先端の物理学理論が融合した先を見据える」
2024年12月18日(水)、市民講座「情報学最前線」第2回「量子コンピュータとは何か?―情報学と最先端の物理学理論が融合した先を見据える」を開催しました。講師は、情報学プリンシプル研究系の添田彬仁准教授で、国立情報学研究所(東京都千代田区)での現地開催とYouTube Liveによるオンライン配信を併用したハイブリッド形式で行い、会場には80名、オンラインでは200名が参加しました。

講座の概要:計算理論の基本から量子力学
添田准教授は、自身の研究の出発点として、幼少期から宇宙や物事の仕組みに興味を抱き、物理学を学ぶ中で量子力学に出会った経緯を語りました。その後、量子力学が情報処理と融合する可能性に魅了され、量子情報の研究へ進んだ背景を紹介しました。
本講座では、統一的な理論を目指す研究のモチベーションに触れ、物理学と情報学が交差する「量子コンピュータ」をテーマに、「量子力学」と「計算理論」の基本的な考え方を解説しました。
まず、日常生活の中で身近な「計算」の例を挙げながら、その本質に迫るための概念として「二進数」や「チューリング機械」を紹介。計算とは、0と1の並びを一定のルールで変換するプロセスであり、この理論が現代の計算機科学の基盤を形成していることを説明しました。
次に、物理学の還元主義と普遍性に基づき、ミクロな世界、すなわち量子の世界を理解する必要性を語り、電子や光が「波」と「粒子」の二重性を持つことを示す二重スリット実験を通じて、量子力学の背景を説明しました。また、波や粒子の性質を理解するためのベクトルや複素数、確率、行列といった数学的概念を簡潔に紹介し、それらが量子状態の理解に重要であることを強調しました。
量子コンピュータの仕組みと可能性
そして、量子コンピュータの計算を表現するための枠組みである、量子回路モデルの特長として、量子ビットの0と1の重ね合わせ状態により並列計算が可能になる点を挙げ、これにより、従来の計算機では非常に時間がかかる因数分解や量子系のシミュレーションといった問題が効率的に解ける可能性があると説明しています。
一方で、量子コンピュータの実現にはいくつかの課題が存在します。具体的には、エラーの制御や外界からの影響を抑える必要があり、多くの研究者がエラー訂正技術の向上に取り組んでいます。添田准教授は、量子回路モデルを高精度で実現する技術が量子コンピュータの実用化を支える鍵であると説明しました。
参加者の声
本講座は、参加者に量子コンピュータという最先端技術への理解を深めるきっかけを提供しました。一見難解に思えるトピックを、物理学や数学の基礎から解きほぐし、専門知識のない参加者にも、量子コンピュータが私たちの日常や未来に与える影響について考える機会となりました。

講演映像のアーカイブはウェブサイトに公開予定です。
次回以降の講座にもぜひご注目ください!
詳細、お申し込みは、下記ページをご覧ください。
https://www.nii.ac.jp/event/shimin/
多くの方々のご参加をお待ちしております!
「情報学最前線」 平成28年度 特別会 Q&A 平成28年度 第6回 Q&A 平成28年度 第5回 Q&A 平成28年度 第4回 Q&A 平成28年度 第3回 Q&A 平成28年度 第2回 Q&A 平成28年度 第1回 Q&A 平成27年度
「情報学最前線」 平成27年度 第6回 Q&A 平成27年度 第4回 Q&A 平成27年度 第3回 Q&A 平成27年度 第2回 Q&A 平成27年度 第1回 Q&A 平成26年度
「未来を紡ぐ情報学」 平成26年度 第8回 Q&A 平成26年度 第7回 Q&A 平成26年度 第6回 Q&A 平成26年度 第5回 Q&A 平成26年度 第4回 Q&A 平成26年度 第2回 Q&A 平成26年度 第1回 Q&A 平成25年度
「未来を紡ぐ情報学」 平成25年度 第8回 Q&A 平成25年度 第7回 Q&A 平成25年度 第6回 Q&A 平成25年度 第5回 Q&A 平成25年度 第4回 Q&A 平成25年度 第3回 Q&A 平成25年度 第2回 Q&A 平成25年度 第1回 Q&A 平成24年度
「人と社会をつなぐ情報学」 平成24年度 第8回 Q&A 平成24年度 第7回 Q&A 平成24年度 第3回 Q&A 平成24年度 第1回 Q&A 平成23年度 平成23年度 第8回 Q&A 平成23年度 第7回 Q&A 平成23年度 第6回 Q&A 平成23年度 第5回 Q&A 平成23年度 第4回 Q&A 平成23年度 第3回 Q&A 平成23年度 第2回 Q&A 平成23年度 第1回 Q&A 平成22年度 平成22年度 第8回 Q&A 平成22年度 第7回 Q&A 平成22年度 第6回 Q&A 平成22年度 第5回 Q&A 平成22年度 第4回 Q&A 平成22年度 第3回 Q&A 平成22年度 第2回 Q&A 平成22年度 第1回 Q&A 平成21年度 平成21年度 第8回 Q&A 平成21年度 第7回 Q&A 平成21年度 第6回 Q&A 平成21年度 第5回 Q&A 平成21年度 第4回 Q&A 平成21年度 第3回 Q&A 平成21年度 第2回 Q&A 平成21年度 第1回 Q&A 平成20年度 平成20年度 第8回 Q&A 平成20年度 第7回 Q&A 平成20年度 第6回 Q&A 平成20年度 第5回 Q&A 平成20年度 第4回 Q&A 平成20年度 第3回 Q&A 平成20年度 第2回 Q&A 平成20年度 第1回 Q&A 平成19年度 平成19年度 第8回 Q&A 平成19年度 第7回 Q&A 平成19年度 第5回 Q&A 平成19年度 第2回 Q&A 平成19年度 第1回 Q&A 平成18年度 平成18年度 第8回 Q&A 平成18年度 第7回 Q&A 平成18年度 第5回 Q&A 平成18年度 第3回 Q&A 平成17年度 平成16年度 平成15年度 市民講座アーカイブ
注目コンテンツ / SPECIAL
 NIIサービスニュース
NIIサービスニュース
 国立情報学研究所
国立情報学研究所2025年度 要覧
 国立情報学研究所 2025年度 概要
国立情報学研究所 2025年度 概要
 NII Today No.104
NII Today No.104
 SINETStream 事例紹介:トレーラー型動物施設 [徳島大学 バイオイノベーション研究所]
SINETStream 事例紹介:トレーラー型動物施設 [徳島大学 バイオイノベーション研究所]
 ウェブサイト「軽井沢土曜懇話会アーカイブス」を公開
ウェブサイト「軽井沢土曜懇話会アーカイブス」を公開
 情報研シリーズ これからの「ソフトウェアづくり」との向き合い方
情報研シリーズ これからの「ソフトウェアづくり」との向き合い方
 学術研究プラットフォーム紹介動画
学術研究プラットフォーム紹介動画
 教育機関DXシンポ
教育機関DXシンポ
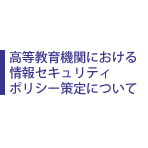 高等教育機関におけるセキュリティポリシー
高等教育機関におけるセキュリティポリシー
 情報・システム研究機構におけるLGBTQを尊重する基本理念
情報・システム研究機構におけるLGBTQを尊重する基本理念
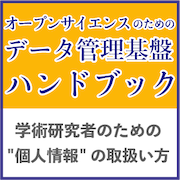 オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック
オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック
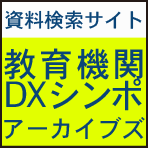 教育機関DXシンポ
教育機関DXシンポアーカイブス
 コンピュータサイエンスパーク
コンピュータサイエンスパーク


