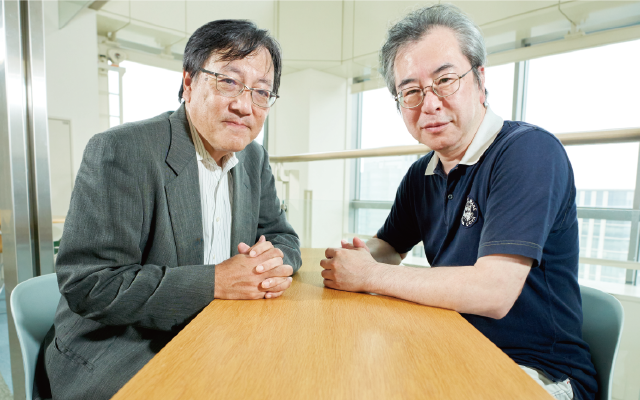Interview
アカデミアとインダストリーのストーリー
最前線の研究に携わるアカデミアの研究者と、産業界で製品を創り出すエンジニア。いずれも世の中を変える技術を生み、育てていく達人だが、両者の間に見えない隔壁があるという。その壁とはいったい何か。アカデミアとインダストリーで、手探りながら協創関係を構築してきた二人に、現在に至るストーリーを聞く。

安里 彰Akira Asato
富士通株式会社
先端技術開発本部システム第一開発部

五島 正裕Masahiro Goshima
国立情報学研究所
アーキテクチャ科学研究系 教授
(敬称略)
「まずは話してみよう」から始まる関係
まずはお二人の簡単なご経歴、そして交流のきっかけについて伺えればと思います。
五島 私は東京大学の准教授から、ちょうど10年前(2014年)に教授として国立情報学研究所に移ってきました。研究テーマは学生の時から一貫してコンピュータ・アーキテクチャを手掛けており、その絡みで、安里さんともお付き合いが始まったという感じです。安里さんは富士通の中でもちょっと珍しい方で、学会にも非常にコミットして頂いていて、それがそもそものきっかけです。
安里 私は一貫して富士通の所属です。3年程前に定年を迎えていますが、現在も嘱託という形で関わっています。もう少し詳しく言うと、前半は富士通研究所という研究子会社に所属し、研究といっても大学におけるそれとは異なり、富士通の製品開発を視野に入れた試作のようなことをやってました。その後、2007年からはスーパーコンピュータ「京」のプロジェクトが始まったのを契機に組織変更があり、私を含むグループが事業部門に移籍、そのまま定年までという流れです。 特に前半の、研究寄りの仕事をしていた時期に、上司の勧めもあって、学会に関わり、研究会の幹事のような役も務めるようになりました。私の性格もあるのかもしれませんが、会社の中にずっといるよりも、そうして外の先生方と交流を持つのが楽しくて、事業部門に移ってからも、そんな関係が続きました。事業部門にいながらも、積極的に外に出ていき、アカデミア方面の方々ともお付き合いがあり、顔も覚えて頂いていたという点では、ちょっと珍しい社員だったかもしれません。 もっとも、五島先生ご本人に関して言えば、学会関係の仕事をするなかでお顔は存じていましたが、当初はその程度でしたね。
そうした状況から、どのように協力関係を進めて行ったのでしょうか。
五島 もともとは、東京大学のある研究室の懇親会で、若手の先生と、その研究室出身の安里さんの部下の方との間で話が進み、何か共同研究のようなものは出来ないかということになった。その時に、私にも声が掛かって、その集まりに加わったというのが、直接のきっかけだったと記憶しています。
安里 もっともその時は、はっきりと「共同研究」という形にまではなっていませんでしたね。共同研究というと、企業側からきちんとお金を出してアドバイスを貰ったり、ということになると思うのですが、その時の集まりはそこまでではなかった。組織としてきちんと契約を結び、ということではなく、ほぼ個人レベルで集まって、「何か面白いことある?」というような感じでした。
五島 そもそも当時の状況でいうと、富士通側にも大学とそこまで緊密に、何か一緒にやるという雰囲気はありませんでした。確かに社内では独自に研究開発は進めているのだろうけれど、外から何かを取り入れようとしている風にも見えなかった、というのもあります。
安里 確かにそれはあったと思います。私としては、富士通の中にいながら大学の先生方とも付き合う立場にいて、いま五島先生が仰ったようなことも感じていました。社内を見渡して、「この人たち、もっと外を見て、先端の研究成果を取り入れていけばいいのに」と思うこともありましたし。
そんな中で、「こんな集まりを持とうと思うがどうか」という話が回ってきた。これはいい話が出てきた、渡りに船だ、と。できる範囲で積極的に進めて行きたい、これで社内の皆にももっと刺激を与えたいと思ったのです。
五島 実を言うと、私は当初、あまり期待はしていなかったんです。一緒に行った先生の中には、企業で作っているプロセッサの特性の実測値が欲しいとか、そんな希望を持っている方もいましたが、私は、どうせ何も出てこないだろうと。
実際に、企業が行っている研究開発の中身は喋れないことが多くて、共同研究レベルになるときちんと秘密保持契約(NDA)も結んで、「どこまで話せる/話せない」をきっちり決めるのですけれど、その時はそこまでも行っていません。
ただ、当初の想像に反して意外なほどに歓迎してもらって、話も聞いてもらって――。最初のうちは、半年に一度くらいでしょうか。会合を持って、今、アカデミアではこういうことを考えている、研究室ではこんな研究をしている、という話を聞いてもらうということが多かった。
安里 そうですね。ですから、「ギブ&テイク」という観点でいえば、その頃は我々はほとんど貰うばかりで、研究の最先端の様子を聞かせていただくという感じでした。
五島 それでも、それ以前に富士通に対して抱いていたイメージからすると、信じられないくらいオープンだったんですよ(笑)。
それが、私がNIIに移ってきてすぐの頃だったと思います。そうしたことを重ねてきて、2020年頃からいよいよ本格的な共同研究の話に移っていくことになります。
交流から得られるもの
̶̶当初の「共同研究」まで至らないミーティングの中で、具体的な研究成果のやり取りなどは無くても得られるものというのは何なのでしょうか。
五島 アカデミアの立場からすると、公知の範囲であっても、自分自身のやっていることを誰かに話すこと自体に意味があるというか、楽しい。それも、実際にプロセッサを作っている人たちに聞いてもらえることに価値がある。もちろん、アカデミアといっても個人差もあると思いますが、特に我々のように、インダストリーに近い立場にいる者としては、やはり自分の考えていることが世の中に出て行って欲しいという希望があるわけです。ただ実際には、それを世の中に繋げていくパスがなかなか存在しない。そんな時に、本格的な共同研究ではなく、雑談レベルであったとしても、自分の喋る内容が何らかの影響を与えて、それで富士通のプロセッサが少しでも良くなっていくのであれば、それはハッピーなことだと思うのです。
安里 私自身は、インダストリーとアカデミア、その両者が見える位置にずっといて、「見えているのに、接点がない」ということに、ストレスを感じていました。特に開発部門のエンジニアたちには、アカデミアの世界で今何が語られているかに、もっと興味を持ってほしい。もちろん本当は、自分で社外に積極的に出て行って交流を広げてほしい。
そこで得た情報をどう使うか、判断はもちろんエンジニア自身がやればいいのだけれど、とにかく、井の中の蛙になって、「今何が起きているのか」を知らずに開発を進めているのでは、特にプロセッサのような分野では、絶対に世界に後れを取ると思っていました。そこで、こうした機会を突破口にして、さらによりよい関係を築いて行ければと思っていましたね。
例えば海外の場合は、企業が積極的に著名大学に寄付講座などを作り、そこで優秀な学生を集めて、どんどん共同研究を進めて論文を出し、賞を取ったりしている。当然ながら、そうした成果は製品にも反映されていく。最近は富士通もそういった動きが少し出てきてますが、当時はまだまだで、いずれはウチもそんな風にしていきたい、という思いがありました。
五島 もともとアカデミアとインダストリーの交流があまり盛んではなかったことについては、日本企業の「自前主義」のような部分も背景にあるのではと思っています。これは程度の差はあれ、日本企業の多くが持っている気がしているのですが、技術を外から買ってくることはせず、全部自社内で産み出すんだという気持ちが非常に強い。しかしそれでは、これからの時代は戦っていけません。少なくともコンピュータ・アーキテクチャの分野では、アメリカと日本では研究コミュニティの規模が開いてしまっています。研究者の層の厚み、関係する人材の数自体が、おそらく一桁以上違います。ですから、研究を行うにしても、よほどすごい戦略を立てて当たらないと、一角に食い込んでいくことすら難しい。そのためには、やはりアカデミアとインダストリーの連携は欠かせないと思います。
見えてきた課題と今後の展望
̶̶協力関係を進めて行くにあたり、特に難しさを感じる点、今後の課題等について伺えますか。
五島 当初に比べると、現在はだいぶ状況は改善されてきていると思うのですが、それでも秘密主義的な部分は相変わらず残っている印象です。
実際に今は共同研究も行っていて、秘密保持契約(NDA)も結んでいるのですが、例えば研究部門と結んでいるNDAと、事業部門と結んでいるNDAとは異なっていて、研究者のレベルでは、事業部がやっていることをどこまで話していいのかが、手探りだったりします。そしてそれを判断するのに、ものすごく時間がかかったりする。アメリカのような、大学研究室と企業との一体感のようなものにはだいぶ遠いと感じます。
安里 ただ、アメリカの場合は、日本のように組織によって人間が厳然と分かれているのではなく、頻繁に人材面でも行き来があるとか、同じ人が両方に所属しているか、そういった環境もあるのではと思います。おそらく、会社とか大学とか、そういった枠組みを越えたところで研究者・技術者のコミュニティが出来上がっていて、その中で活発に情報のやりとりも行われている。そうしたカルチャーは日本には無いものですね。
もうひとつ、私の側から言うと----私自身は最近は共同研究等に関わっていないので具体例とかではないですが、やはり企業側の意識の問題は残っていると思います。ここまでで、徐々に改善したものはあると思いますが、やはり企業の閉鎖性のようなものはある。たぶん、現場レベルでは問題意識を持っている人はいると思うのですが、やはり最終的には経営判断としてgoを出す人たちがもっと変わっていってほしい。
五島 いや、特にここ5年くらいでしょうか。だいぶ変わってきたと思いますよ。それは安里さんがきっかけを作ってくれたのも大きいと思う。やはりミーティング等で、設計部隊が現実に困っている問題についてアドバイスして、それが功を奏してうまく行った、というようなことが少しずつ積み上がっていって、それにつれて信頼関係も増している気はしますね。
いずれにしても、そのような、アカデミア側からの貢献部分、いわば"グッド・プラクティス"を、規模的にもの数的にも、もっと積んでいく必要はあると思っています。本当のところを言えば、アカデミアは企業のことなど考えずとも、ひたすらに良い研究をして、それを企業側が見出して応用してくれるというのが理想的だと思いますが、なかなかそうはいかない。やはり、アカデミア側から、「こうなるとよくなりますよ」ということを、積極的に発信していくことも必要だと思っています。実際には、ここ最近は富士通側から「ここ、どうしたらいいでしょう」と聞いてくることも増えて、昔はそんなことはなかったので、隔世の感を覚えているところではありますが。
もっとも、10年かけてここまで変わってきた......ではあと10年でどこまで変わるのか。10年経ったら私も定年ですから、このペースで大丈夫なのかというのはありますね(笑)。もっとドラスティックに変わって欲しいところではあります。
安里 私自身はもう定年を迎えていて、嘱託での退職もあと数年というところなので、自分がどうこうというのはありませんが......。それでも、これまで10年かけて積み上げてきたものが、よりうまく回っていくようになってほしいですね。
取材・構成:川畑 英毅/写真:杉崎 恭一