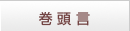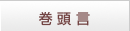マシュー・H・ディック(北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門)

本稿は校正業務についての二部構成の論考の後半部分である。前半は SPARC Japan のニュースレターにすでに掲載されている。そこでは、校正作業について説明し、出版プロセスにおける校正業務の位置づけを明確にした。とりわけ、非英語圏出身の著者 ‐ 英語で書いているが、母語は英語ではない執筆者 ‐ が高い割合を占めているようなジャーナルの事例を扱った。本稿では、ジャーナルの書式とスタイルが出版プロセスにどのような影響を及ぼすかを考察し、最後に論文著者に対するアドバイスをしておきたい。
● ジャーナルの書式とスタイル
私が40年ほど前に学部生だった頃、期末レポートの参考文献の書き方として、教授陣はCBE(Council of Biology Editors、現在はCouncil of Science, CSE)のスタイル・マニュアルに従うようにと指定していた。当時の私は、後々まで役に立つことを学んでいるのだと思っていたが、実際にはほとんどのジャーナルはそれぞれ別の参考文献の書式を採用しており、しかも世の中にはたくさんのジャーナルがあることに知り、驚く破目になった。Biological Abstracts (http://thomsonreuters.com/) は今や、100カ国にわたる4200誌の生命科学系のジャーナルの論文を扱っている。科学文献のリファレンスに4200通りもの異なる形式があるとしたら、それだけで大変だろうと思われるかもしれないが、実は、句読点、略称、大文字表記、語順、フォント、空白、引用形式が多様であることを考えると、それは何十万通りにもなるのである。
各々のジャーナルが別々の参考文献の書式を採用しているということは、書かれた言葉の歴史において時間と労力の浪費の最たるものであるに違いないのだが、驚くべきことに、どうしてこのようなことになっているのか、納得できるような答えを与えてくれる科学誌編集者に私は出会ったことがない。たとえば、あなたが参考文献欄を Nature の書式から Science や PNAS のそれに書き換えたことがあるならば(有意義な研究成果を出版するために、インパクト・ファクターや知名度のランクを下げるなど、ここでは何でも思いついた二、三の雑誌名を思い浮かべて欲しい)、私の述べていることの意味を理解していただけると思う。この理解し難い状況は、どこかで掲載拒否された論文を再利用して、他へ再投稿をする輩を思いとどまらせるために存在していると考えられているかもしれないが、実はそのような作用をまったく果たしてはいない。著者は掲載のチャンスがあると思えるジャーナルのなかから、最もインパクト・ファクターの高い順に投稿し、拒否されれば別のジャーナルに投稿するものである。投稿のプロセス全体が時間のかかる退屈な作業で、安易な投稿を思いとどまらせる。ゆえに、よそで掲載拒否された論文の参考文献欄の書式をいちいち変更することは、ただ、著者と編集者の双方に無用で面倒くさい作業をさせるだけのことであり、全地球規模で見れば、毎年このような作業に費やされた各人の時間は積もり積もって何十年間にもなることだろう。いろいろな会社から出ている参考文献作成のソフトウェアは書式変更に対応するとされているが、こうした製品を試して悪戦苦闘した結果、結局は参考文献欄の書式変更を手動で行なった方が速いし正確でもあることを私は発見した。
さまざまな参考文献の書式が存在することについて、考えられる唯一の理由は、各ジャーナルが独自のアイデンティティを持てるということだ。ジャーナルが独自性を追求する度合いはさまざまであるが、ジャーナルの名声が高いほど、全般的な書式とスタイルの規定は厳密になる。私が Zoological Science の校正作業を始めた頃、このジャーナルはルーズなあるいはオープンな書式を採用しており、スタイル、見出しと小見出しの位置、図式や図表のつけ方などは統一的でなく、規定もされていなかった。こうしたやり方が悪いというわけではなく、事実、規模の小さなローカルな学会の多くがそうしている。だが、Zoological Science はもはや弱小の学会ではなく、アジアで最もよく知られた学会のジャーナルだった。私は、論文の掲載のされ方によっては、読者はジャーナル全体のクオリティの良さを感じとるものではないか、ひいては、なんらかの形で被引用度の引き上げにもつながるのではないかと考えた。半年ほど経ってから、私は独断で、校正段階ですべての論文を統一された書式へと変換することに決めた。独断で決めてしまったのはなぜかというと、このことで編集会議やのみならず諮問委員会までもが開かれて、果てしない議論がなされた後に妥協点に行き着くか、もっと悪ければ何も決まらないというような事態になることを恐れたためである。*¹
一貫したスタイルを維持することは、テキストの細かな点にまで及ぶ。例えば、数字記号や単位の前後に空白を入れるかどうか(mean=20g と mean = 20 g)、よく使われるラテン語の語句や略語をイタリック体にすべかどうか(i.e. と i.e.、in situ とin situ)。校正者として私は、一貫性を保つためにどのように編集すべきか知る必要があったし、また、何度も言うようだが、一貫性は読者の感覚に大きく寄与すると考えた。上記の点については、私は通常、The Chicago Manual of Style(15版、シカゴ大学出版局)で推奨されている方法に頼ることにした。また、編集委員長が私の意見を取り入れた形で、毎年 Zoological Science の執筆者要項を改訂してくれたので、著者が守るべきスタイルの慣例を数多く追加できた。これにより、以前は校正段階でいちいち決めなければならなかった諸点が形式化されたことで、私の業務が楽になった。
英語の用法、スタイル、書式、綴り、文法、句読点等において、何が正しく何が間違いなのか。今日では、英語の使い方のルールは、職業上この言語を使用している人々が構成する語法諮問会議(usage panel)によって決定されている。たとえば、名高いAmerican Heritage Dictionary(AHD)の Usage Panel は、およそ200人の著名な言語学者、作家、ジャーナリスト、放送者、学者によって構成されている。議論の的になっている語法について、パネルのメンバーが質問表に答え、大多数のメンバーが選んだ語法が推奨された語法となる。しかし、もし70%のメンバーがある語法を他より良いとしたとしても、残りの30%が他の語法を好むならば、そちらを使い続けることもあるということにも留意したい。白黒の決着がつくものではなく、あるのは濃淡の差であり、ある世代には好まれる語法が、世代が若くなると異なるということもありえる。
シリアル・コンマがその良い例だ。小学校から高校まで私は、ものを列挙する際の and の前のコンマ(シリアル・コンマという)を使うようにと習った。たとえば、“I bought roses, violets, and tulips.” であって、“I bought roses, violets and tulips.” ではいけない。1960年代から現在までの間に、この用法は変わり、作家や新聞社はシリアル・コンマを省略するのが通例になった。とはいえ、この省略は時には曖昧さももたらすことになった。たとえば、次の文を見てみよう。
This formula is straightforward, concise, and simple.
これを次のように書くと異なってしまう。
This formula is straightforward, concise and simple.
第一の文例では、単刀直入、簡明、単純という、公式の三つの性格が並列されている。第二の文例では、簡明かつ単純(concise and simple)という部分は、なぜ公式が単刀直入(straightforward)であるのかを詳しく説明する役割を担う。このような意味上の違いは、シリアル・コンマが一貫して使われ続けていたならば、明確だっただろう。私はこの考えに基づいて、 Zoological Science の校正業務では、シリアル・コンマを使うことにしている。シリアル・コンマの省略は現在の通例となってはいるが、Chicago Manual も私と同じ考えに立っている。

注釈
| *¹ |
編集委員会の仕事の遅滞というケースは稀ではない。英国の Journal of Natural History は何年間も、もう使っていない古い執筆者要項をネット上に記載し続けて、校正者の作業を倍増させていた。 |
● 著者へのアドバイス
Zoological Science 掲載のために私が校正する論文の視角や質は多様である。大学院生による研究者として初めて英語で書く専門分野に特化した論文もあれば、一流の生物学者による大論文や書評もある。そのなかには、英語での執筆に熟練した英語圏、非英語圏出身両方の著者がいる。校正者としての私の仕事は、筆頭著者の英語の執筆経験と熟達度に反比例する。一般に、非英語圏出身の著者はすべからく、冠詞や代名詞の用法などいくつかの同じ間違いを繰り返す傾向にある。これらの用法の正確さは英語という言語にとりわけ特有のものであるけれども、幸運なことに、ネイティブの校正者が施さねばならない修正は機械的校正であるので、比較的に単純な作業ですむ。冗長さや曖昧さにつながる、まずい構文や段落構成などがあると、原稿が読みづらいものになっている度合いが高いので、実質的な校正が必要となり、残念ながら、それはより困難で時間のかかる作業となる。肯定的な見方をすれば、こうした不備は、執筆経験の少なさに由来するものであるから、英語圏・非英語圏出身にかかわらず、著者が学ぶにつれて減少すると考えられる。本節では、実質的なレベルで執筆力の向上に役立つような提言を行いたい。
明瞭な著述は明瞭な思考の結果である
もし、論文著者が研究の目的や研究結果の分析、解釈について明確な考えを持っていないならば、それらについて明瞭に記述することはできないだろう。研究を終えた後に論文を書くことを面倒な作業とみなすよりも、論文著述は研究の欠くべからざる一部をなすと考えるべきである。私が研究論文を書くのは、しばしば得られた成果の提示や説明が難しいために、再評価、適格性の認定、他の提示方法、またあるいは他の説明方法が必要となる場合である。
批評や編集は著述力の向上につながる
生まれながらに書き方を知っている者はいないし、ましてやうまい書き方を知っている者はいない。他の技術と同様に、著述力も長くたゆまない練習とフィードバックによって向上する。経験の少ない著者にとって最良の方法は、経験のある人に改良点を原稿に直接書き込んでもらい、その後それらの改訂箇所をデジタル・ファイルに書き入れることだ。このプロセスをふむことで、その著者は自動的により簡潔で正確な書き方を学ぶだろう。これは英語圏・非英語圏出身者のどちらにもあてはまることだ。特に、非英語圏出身の未熟練な著者は、経験を積んだ、できれば英語圏出身者に投稿前の原稿を直してもらうように頼むべきである。 Zoological Science に掲載されている論文のなかで、共著者に少なくとも一人の英語圏出身者を含むが、筆頭著者が非英語圏出身者である場合には、滅多にあるいは一度も英語圏出身著者に校正してもらったことがないことが多いと知り、私は驚いた。非英語圏出身者は特に、共著者である英語圏出身者に、原稿をできるだけ厳密に直してもらうよう頼むべきであり、訂正箇所を詳しく読んで学ぶべきである。
32年前、私が筆頭著者となった最初の論文を出版した時、パソコンやワープロなどまだ存在していなかった。私は第一稿を手書きで書き、提出稿をタイプした。その後の改訂もすべてタイプした。ページの途中で一行抜けると、そのページ全部をタイプし直さなければならなかった。記述と改訂の物理的なプロセスは今日ではずっと容易になった。それだけでなく、ワープロのソフトウェアにはスペルと文法の間違いをチェックする機能があり、強力な校正ツールでもある。文法チェック機能は、不自然な語法を指摘し、別の語を提示するので、格好の学習ツールともなりえている。提示される言葉がいつも有用とは限らないが、書き手には、ソフトウェアがなぜ特定の文章や表現を問題ありと見なすのかを考えてみることで意義があるだろう。
著者は執筆要項を読むべきである
著者にとって、執筆要項を読むほど退屈なことはないであろう。まったく読まない人もいるかもしれない。しかし、執筆要項を読まない人はその代償を、知らぬ間にかなり高くつく代償を払っていると言いたい。Zoological Science の校正者の私の手元に届いた論文の約5%は、明らかに他のジャーナルのスタイルで参考文献欄が書かれていた。Zoological Science の書式を知悉している査読者たちは、当然このような論文に気がつき、次のように考えるだろう。1)その論文は他のジャーナルで掲載拒否され、再利用の形で投稿されてきた。2)著者は、適切な書式に揃えることすらしないほど、論文の出来に配慮していない。こうした結論は査読の結果にも影響を及ぼすかもしれない。例えば、査読者はその論文が他誌で拒否された理由を探し始めるかもしれないのだ。
Zoological Science では、校正作業に入る前に、論文が書式に則っているかどうかを確かめるメカニズムがなかった。掲載を受け付けるよりも拒否する割合が大きい、知名度の高いジャーナルの場合、審査役の編集者(あるいはパネル)が、もっと積極的な役割を果たす。Science や Nature、PNAS のような一流ジャーナルに、明らかに書式が滅茶苦茶な原稿を投稿することは、身の破滅を招く行為だ。毎月何百もの原稿が届くというのに、著者が所定の書式にきちんと揃えられないほど無知か無配慮で、おそらく再利用しているような論文を一顧だにする必要がどこにあるだろう。インパクト・ファクターの長い階梯をどれほど下れば、書式の遵守の厳密さがやわらいで、掲載許可が得られるのかはわからないが、論理的に考えれば、出版する数に比して送られてくる原稿の数が多いジャーナルであればあるほど、厳密さはより重要な要素になる。
Zoological Science の場合、執筆要項を無視する著者のツケは、校正者を含む編集スタッフが余計な仕事を強いられる形で払った。ジャーナルは私に毎月決まった額を支払い、私の仕事を軽減しようとする気はほとんどないようだった。とはいえ、私の時間も無限ではないのだから、参考文献欄の書式の直しに時間をとられると、原稿の他の部分に割ける時間が減ってしまい、全体としてクオリティが下がることになった。校正者への支払いを契約ごとにしたり、時間決めにしているジャーナルの場合には、著者の怠慢から生じた余計な編集作業は、コスト増という結果を招くだろう。
短い方が良い
著述において、語数は少ないほど良い。簡潔な英語の文例として、サミュエル・T・コールリッジ(イギリスの詩人、1688-1744)の有名な警句の定義ほどふさわしいものはないだろう。
警句とは何か?小人のようにコンパクトで、そのボディは短く簡潔であり、その魂は知力である。
科学の研究論文ではコールリッジほどの技能は必要ではないが、過剰な語数は書き手にも読み手にも余計な手間をかけるし、冗長で凡庸な著述になりかねない。校正者として私は、できるだけ余計な言葉を削除するよう努めた。次の二つの文例を見てほしい。一つ目は、経験の浅い書き手によるもので、私がしばしば出会ったスタイルである。二つ目は、それを編集したものだ。
There were two ways in which differential expression was demonstrated by the cortical cells. First, the fact that the cortical cells still retained the stain indicated that they were probably expressing mRNA from the gene that we examined.
余計な言葉(下線部)を削除した結果、次のように短くなった。
The cortical cells demonstrated differential expression in two ways. First, since they retained the stain, they were probably expressing mRNA from the gene we examined.
後の文章の方が、前の文章より13語(34%)少なくなっているが、意味するところは同一である。そして、結果的にずっと読みやすいものになっている。ここで挙げた文例では、受動態を能動態に代え、代名詞を使う文章の構造にして繰り返しを省き、”there are” とか “the fact that” というような構文を廃した。他に、省略法も語数を減らす方法である。省略法とは、文脈から読み取れる言葉を不必要なものとして省くやり方である。次の文例では、下線部の部分が省略法で省くことができる。
The best fit model of DNA substitution by the Akaike information criterion (Akaike, 1974) was the Tamura-Nei model with invariant sites and the gamma shape parameter (TrN +Ⅰ+Ґ). However, the two best-fit models of DNA substitution were not congruent with each other. Of these, the more parameter-rich model of DNA substitution, GTR +Ⅰ+ Ґ, was used to estimate ML distances.
語数が多くなる構文に気をつけて練習を積めば、どんな著者も簡潔に書けるようになり、著者自身と編集者、読者の労力を大幅に減らすことになる。
経験の浅い著者は、大がかりな重複も多い。おおがかりな重複とは、一つの原稿のなかで、文章や段落をまるごと、逐一あるいはそれにほとんど近く二回以上繰り返すことである。重複箇所は、点滅するネオンサインのように目立ち、読者は「これをなぜまた読んでいるのだろう?」と不思議に思う。よくある間違いは、序論や研究結果を述べている節の文章をまるまる繰り返してしまうことだ。研究結果をいったん詳細に論じたならば、著者は議論の節では簡潔な言い換えですますべきである。例えば、「水温と産卵との間の負の相関を示す私の研究結果は・・・」のように。
段落構成を学ぶことが明確な著述につながる
読みやすい著述が明瞭で簡潔なものであるとすれば、段落構成がなっていない著述はその対極にあるものである。段落がきちんと構成配置されていないと、読者は何が書かれているのか理解するために、じっくり読まねばならなくなる。段落分けがなされていない場合、原稿の何頁にもわたる長い一塊の文章になってしまう。まだ仕事の経験が浅かった頃、私は段落構成がなされていない文章を読み、理解できない自分が馬鹿だと自分を責めることがあった。私自身もそんな文章を書いていたと思う。後に、学部学生にライティングを教えるプロセスのなかで、上手に段落分けされた文章はすべて、共通してシンプルな構造を持っていることを学んだ。これを知って後は、私は良い書き手になったし、以前より容易に他の著者の段落構成を修正できるようになった。
段落構成のシンプルなルールは以下のようなものだ。その段落が何について書かれているのか、あるいは結論やトピックに関連する情報のみを示すトピック・センテンスを各段落に入れる。トピック・センテンスの場所はどこでも良いし、分割されていても、また繰り返しても良いが、とにかく必ず入れなければならない。図1では、どこにトピック・センテンスを置くかで決まる段落構成のさまざまなタイプを示した。段落を良いものにするために他にできることは、主張を支えるために証拠や例を示す(段落の展開)、移行句や文を使って論理的に文章をつなぐ(段落の一貫性)ことなどである。しかし、トピック・センテンスが欠けていれば、段落は最初から失敗している。
変化に富んだ段落構成は、よりダイナミックで面白い著述につながる。私は、ある非英語圏出身の著者がプロフェッショナルの編集サービスを頼んだケースを覚えている。原稿はほぼ完璧で、私がすべきことはほとんどなかった。しかし、その原稿はある点で際立っていた。長い研究成果の部分で、すべて同じ段落構成(図1のC)をとっていて、同じ文体のトピック・センテンスで締めくくられていた。「これらの結果が示すところは・・・」。文章は明瞭だったが、非常に退屈な感じがした。
明瞭でダイナミックな段落を書くには、スティーヴン・ジェイ・グールド(1941-2002、進化生物学者、エッセイスト)を読むといい。恐らく、現代における生物学分野の最も優れた書き手である。次の文章は、”Evolution as Fact and Theory” からのものである。(http://www.stephenjaygould.org/library/gould_fact-and-theory.html)
さて、進化は理論である。また、事実でもある。事実と理論とは別物であり、確実性の階梯の横木でもない。事実は世界のデータである。理論は、事実を説明、解釈する思考の構造である。事実は、科学者たちがそれを説明する論敵の理論を論破しているからといって、消えてしまうわけではない。重力に関するアインシュタインの理論がニュートンの理論にとって代わっても、林檎が途中で落ちるのをやめるわけではないし、結果が宙ぶらりんになるわけではない。そして、人間も猿に似た祖先から進化してきたのであって、それはダーウィンや他の人々によってそのメカニズムの説が出されたこと、あるいはいずれ発見されるかもしれない説とはかかわりなく、起こったことなのである。
ここでは、トピック・センテンス(下線部)が段落のほぼ冒頭に置かれ、その後にトピックが詳しく語られている。この文章は図1のAのタイプといえよう。
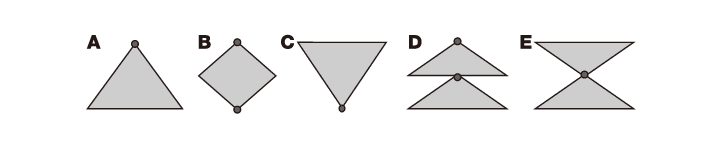
| 図1: トピック・センテンスの位置(小さな丸)に基づいた段落のタイプ |
| |
(A) |
トピック・センテンスが段落の冒頭かその近くにあり、以降はそれをより詳しく論じる、または支える証拠を示す。 |
| (B) |
段落の最初の方で全般的なトピック・センテンスを掲げ、そのトピックを掘り下げ、さらに特殊な側面に焦点をあて、最後に特殊な側面を加味したトピック・センテンスを再度提示して締めくくる。 |
| (C) |
証拠の提示や一般論で段落を始め、凝縮して結論、推論に至り、最後の方でトピック・センテンスを提示する。 |
| (D) |
トピック・センテンスを二つに分け、前半である側面を論じ、後半で別の側面を論じる。 |
| (E) |
証拠の提示や描写から始め、トピック・センテンスを提示し、さらにそれを詳細に論じる。 |
● 結論
本稿の趣旨は、読者に科学研究論文出版のプロセスについて、そこにおける校正者の役割について、校正の度合いを決める要因についての知識を与えることだった。比較的小さな国際的なジャーナルで、主に非英語圏出身著者によって書かれた英語論文を掲載している場合、校正者の業務は膨大になる。このような著者による論文は、機械的・実質的編集作業の両方を必要とするからである。実際にどれほどの校正作業がなされるかは、次の諸要素の妥協点で決まる。すなわち、制作コスト(ジャーナルが校正にどれほど支払えるか)、編集方針(スタイルと書式の一貫性がいかに編集作業の量に影響するか)、論文の質(どれほどの改訂を必要とするか)、便宜性(できるだけ早く、できるだけ安く出版したいという著者の願いとそれをかなえてくれそうなジャーナルの選定)である。出版コストの上昇と出版か(特に英語で国際的なジャーナルに載せる)自滅か、という著者へのプレッシャーの増大によって、今後、校正者の役割がどのような変化を遂げるかは興味深いことになるだろう。
|