永井 裕子(ながい ゆうこ)
社団法人 日本動物学会 事務局長・UniBio Press代表/筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 博士後期課程
● はじめに
学術情報の流通は、書籍やジャーナルによる冊子体が流通することよって、長く行われてきた。情報は冊子が、手に取られ読まれることで、人から人へ渡されることで、流通した。グーテンベルグによって、それは爆発的にもたらされたものだと言えるが、それ以前でも、羊皮紙やパピルスに書かれた「本」によって、様々な情報は人々の間で流通していた。書かれたものは、同時に『保存』を意味した。そして、小説、詩、エッセイなどと共に、学術論文も、書籍、ジャーナル冊子によって流通する長い時代を経て来た。しかし、学術情報が流通するという意味は、小説が人々に好まれ、版を重ねて読まれることとは、根本的に異なる。学術情報は、積み重ねられ、新たな科学的発見をまた生み出すための、源となるものである。まさに「巨人の肩の上に立つ」の言葉通り、多くの実験、思索、研鑽、アイデアの積み重ねからの「知」を基に、その上に立脚して、科学は日々進展している。
さて、インターネットを介した学術情報流通が、一般化した今、書籍はここでは別にするが、「ジャーナルを出版する」という意味は大きく変化した。より良い科学情報やそのジャーナルに相応しい情報を査読に基づいて、ジャーナルを出版することは変わることはない。だが、冊子を印刷することと、学術情報を web サイトにアップするということは共に「ジャーナルを出版する」ことであるが、実際には、大きく、異なる。かつての冊子出版では、紙や写真の質以外は、製作の方法も総じて変わらなかったが、電子出版を行うことには、以下のような、プラットフォームに関する出版する側の検討点を常に抱えている。
|
1. |
公開するプラットフォームが備える機能について |
|
→ |
開発力を相手方に期待するのか、または学会等で開発するのか |
| → |
新機能の有効性を学会等で解析、検証できるのか |
| 2. |
プラットフォームのコンテンツ様式について |
|
→ |
他のデータベースとのスムーズな相互連携は可能か |
| → |
「保存」の観点 |
| → |
移築時の互換性問題 |
| 3. |
使用するプラットフォームが持つ知名度、もしくは研究者の認知度 |
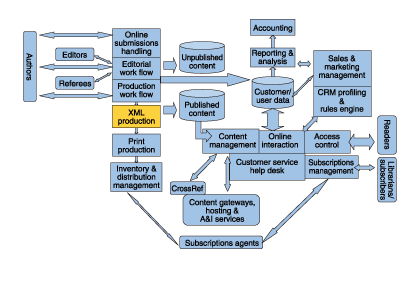
図1: 21世紀初頭におけるジャーナル出版ワークフロー
出典: Mark Ware (2007) Journal Publishing System: outsource or in house?, Learned Publishing, vol. 20, no. 3, figure 1
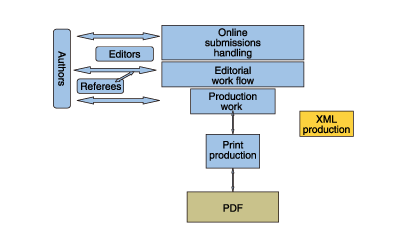
図2: 日本の電子ジャーナル制作過程
冊子を出版することが印刷を意味する時代だったように、論文を web にアップするという営みを行うだけでは、ジャーナルの地位をもはや高められない。冊子時代には考える必要がなかった「研究者により良く見せる、より良く届ける」といった可能性を持った今、それらを念頭に置かねばならなくなった。それは、技術による圧倒的な変革、それも様々な動きに、我々は、常に対応し、また追わねばならないという問題が生じているからだ。プラットフォーム維持、宣伝、販売などを含め、「学会等がどこまで自前で何をやるのか」という問題も実際には検討事項として付け加えることになる。ここで、2011年現在、海外における標準的な出版フロー(図1)と我が国の出版フロー(図2)を図式化したものを提示する。我が国の出版社すべてが、XML 作成を行うにあたり、海外の標準的な在り方を獲得しているとはいえない状況がまだ続いているためである。
我が国における出版が、なぜ、XML 作成に向かわなかったかは、いくつかの要因があげられるだろう。以下に列挙する状況が、互いに影響しあって、現況があると筆者は考える。
1. |
どの学会も利用できることを第一義においた J-STAGE は XML を電子ジャーナル製作のスペックにすること、もしくは早期にスペックを XML に変更することは難しかった。(来春リリースされる J3 は XML を標準とする) |
2. |
科学研究費補助金公開促進費定期刊行物の補助対象が、長く冊子体の直接出版費にあり、また、採択に当たっては、冊子の売り上げ数が重要視されてきた。そのため、日本の学術出版市場では、冊子体印刷に海外と比べ、比較的需要があった。冊子印刷→ PDF 作成という流れも強固で、Word から XML をはきだすといったフローには、ならなかった。 |
3. |
商業出版社からジャーナルを出版する学会は、すでに、MML ベースの電子ジャーナル出版になっていたはずであるが、学会が製作フローにまで係ることは多くはなく、また電子ジャーナル製作や公開システム等についての情報を学会が得るような場も我が国では少なかった。 |
本稿では、21世紀におけるジャーナル出版は、冊子印刷時代とは、大きく異なるという認識にあらためて立ち、ジャーナル出版に際し、もしくはIRを利用しての紀要出版を検討する際に、参考となる情報をまとめることとする。具体的には、2011年秋における プラットフォーム、査読システムについてである。
● ジャーナル出版の変容 ―海外動向と日本動物学会を一例として
具体的な情報をまとめる前に、この約20年ほどのジャーナル出版の変化を概観する。
1993年からは始まるのは筆者が就職した年であるため。それ以外は、学会出版として、変化があった年である。(表1参照)
表1: ジャ−ナル出版の変容 −海外動向と動物学会を一例として−
| 日本動物学会の状況(学会の一例として) |
学術情報海外動向と国内外社会状況 |
 |
| 1993年 |
冊子発行部数
投稿・査読
科学研究費補助金
ジャーナル発送費
ジャーナル製作費 |
3,500部
郵便による原稿のやりとり
10,180,000円
1,235,740円
13,734,818円 |
1月20日
3月18日
4月1日 |
ビル・クリントン米大統領就任
のぞみ運転開始、1時間に1本走行
Joint Infomation Systems Committee 設立 |
| ジャーナル出版業務は、冊子を間違いなく期日までに製作し、会員へ届けることがジャーナルを出版することだと、著者は考えていた。商業出版社からは、ジャーナルの委託販売と出版、編集作業契約に関する申し出が相次いでいた。しかし、出版コストは高く、理事会では、商業出版社に対して、否定的な意見が多かった。理由は、学会独自のジャーナルであるという理事の認識によるものと思われた。 |
Elsevier は1991年より、The University Licensing Program (TLIP)プロジェクトを開始した。その後、Elsevier Electronic Subscriptions(EES)としして販売され、現在の ScienceDirect となる。また、海外学会では例えば、Society for Scholarly Publishing Seminar で以下のような講演が行われていた。
10月14日 STM Publishing 101: Content and Editorial Basics and Digital Workflow |
 |
| 1999年 |
| 学会 J-STAGE での電子ジャーナル公開開始 |
1997年
1998年4月
1998年7月
6月26日
~7月1日
|
SPARC USA 開始
OF MAKING MANY BOOKS THERE IS NO END Report on Serial Prices for the Association of Research Library, Ann Okerson 公開
Microsoft Windows 98日本語版発売
ブタペスト会議開催 |
冊子発行部数
投稿・査読
科学研究費補助金
ジャーナル発送費
ジャーナル製作費 |
2,800部
郵便による原稿のやりとり
11,610,000円
3,488,795円
31,665,535円 |
J-STAGE でのジャーナル公開は フリーアセス(オープンアクセスではない)であった。フリーアクセスであったのは、システムを制御して、会員だけにジャーナルを閲覧させるシステムを学会自らで行うだけの技量もまた予算もなかったため。そこには、電子ジャーナル販売をするという発想はなかった。
電子ジャーナルでの公開は「会員」のためだと筆者は考えていた。また電子ジャーナルへ転換することで、「経費」は削減されるとも考えていた。しかしこの段階では、出版経費は削減されておらず、また、経費削減へのその具体策もわからなかった。 |
米国では、すでに1990年代半ばから、Serials Crisis の様相を呈していた。 Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition(SPARC)は、学術情報流通を研究者、図書館、学会に取り戻そうとして起こった、米国 Association of Research Libraries 先導の運動。Ann Okarson による報告書はシリアルズ・クライシスを振り返る折には、今後も引用される重要な報告書と言える。
2000年 BioMed Central 設立 |
 |
| 2003年 |
| SAPRC Japan 開始 |
Open Access 運動活発化 |
冊子発行部数
投稿・査読
科学研究費補助金
ジャーナル発送費
ジャーナル製作費 |
1,450部
郵便による原稿のやりとり
1,900,000円
2,352,476円
20,532,476円 |
2月1日
4月1日
7月21日
10月10日 |
スペースシャトルコロンビア、大気圏再突入後、テキサス上空で空中分解。宇宙飛行士7名全員死亡
郵政事業庁が郵政公社となる
北島康介100M平泳ぎで金メダル
最後の日本産トキ「キン」死亡 |
| 日本動物学会は SPARC Japan へ参加。日本哺乳類学会、日本哺乳動物卵子学会と共に NPO 法人 UniBio Press 設立。図書館電子ジャーナル購読を目指す。Open Access 運動活発化。我が国では、ジャーナルを web で公開することが、「購読モデル」を獲得するより、重要かつ最先端のジャーナル公開と考える学会が多かった。プラットフォームの知名度、コンテンツのスペック、ビジネスモデルとしての Open Access が考慮されていたかどうかは不明。 |
SPARC USA は2003年7月1日に Model Business Plan: A Supplemental Guide for Open Access Journal Developers & Publishers を作成、ビジネスモデルとしての Open Access が支援を明確にした。 |
 |
| 2007年 |
冊子発行部数
投稿・査読
科学研究費補助金ジャーナル発送費
ジャーナル製作費 |
1,500部
電子投稿(2006年6月開始)
7,900,000円
1,119,444円
13,089,090円 |
2004年
2月10日
5月15日 |
National Institutes of Health(NIH)は公にPublic Access Policy 検討を開始した。
バラク・オバマ2008年アメリカ合衆国大統領選
予備選である民主党予備選挙立候補表明
Thomson が Reuters を買収 |
| UniBio Press(日本鳥学会、日本古生物学会、日本爬虫両棲類学会、日本哺乳類学会、日本哺乳動物卵子学会、日本動物学会)BioOne. 2コレクションの一部として、海外図書館販売開始。 |
NIH Public Policy 策定は、Open Access とは異なるが、Open Access 運動そのものには大きな影響を与えた。例えば、学会のみならず、商業出版社における著作権 Policy 検討の折「標準モデル」として考えられた。 |
● プラットフォーム
電子ジャーナルを公開するプラットフォームは常に進化をしている。それは、コンテンツを格納する「箱」ではなく、現状では、宇宙の中に存在する星団のように、拡がりを持ち、その中では、常に、想像を絶するような、革新と、それに伴うサービスが研究者に提供され続けてもいる。学会は、様々な機能を持つ、最新のプラットフォームを選べる立場にあるが、重要な点はコストである。このコストは、いまや、ジャーナル出版に必要な基本コストであり、出版経費のひとつに計上するものとして考える必要がある。商業出版社にジャーナル出版を委託されている学会は、プラットフォーム使用料を考えられたことは恐らくないことだろう。だが、そのコストがどこで支払われているのかは意識する必要はある。ここでは、日本の学会または図書館が、電子ジャーナルを公開、発信することが可能ないくつかのプラットフォームについて、紹介をする。また、国立情報学研究所、私自身は、以下に紹介する企業やその関係者と経済的または個人的な関連は一切ないことをあらためて付記させていただく。記した内容は、それぞれの代理店等に確認を行った。 SPARC Japan セミナーでは、過去に、米国から、または英国から講演者を招へいし、セミナーを行った。それぞれの講演については、現在、閲覧できるURLを記した。また、自らの重要な論文をどこでどう発信するかは、まさに、そのジャーナルの特殊性や学会の事情、分野にも依拠し、その決定はまさに学会の判断に委ねられるものである。
1. J-STAGE
我が国最大の国営プラットフォームともいうべきもの。国の事業として JST が運営しており、論文の投稿・審査・査読から公開までの一連の工程をシステム的にサポートしている。コンテンツのアップロードは、学会、もしくは学会が印刷を依頼する印刷会社等が行う。J-STAGE の基本的フォーマットは現在は bib 形式。2012年3月にリリースされる J3 は XML をその基本的フォーマットとし、あらゆるデータベース、異なるプラットフォームへの移築が容易になる予定。日本の学術誌700誌以上が利用。プラットフォーム使用料は無料。国の事業であり、「競争入札」を要するため、プラットフォーム事業を行う業者は、時に変更されている。
2008年12月16日、国立情報学研究所で開催された SPARC Japan セミナーでの以下の J-STAGE 講演を参照。
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/2008/pdf/121608/2_J-STAGE_Next_20081216_rev2.pdf
2. Atypon
1996年からソフトウエア、ホステイング、システム開発を手掛ける。学術情報流通の変革に則した技術やサービスを学会出版者に提供している。クライアントは、IEEE から J-STORE、CrossRef まで多様。BioOne も2009年1月から Atypon をプラットフォームとして使用している。2008年10月 Atypon から出された白書1 は、21世紀のプラットフォームのあり方を明確に説明するものである。
2008年12月16日、国立情報学研究所で開催された SPARC Japan セミナーでの、以下のプレゼンテーションを参照。
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/2008/pdf/121608/3_Chris_NII%20Tokyo%202-1.pdf
掲載される論文数などによって、プラットフォーム使用料は異なる。複数学会での使用が経済的。お問い合わせは株式会社アトラス(東京都中央区日本橋)まで。
3. Ingenta
1998年に設立。出版、情報に関わる技術とサービスを提供。2007年2月より、Publishing Technology の一部門となる。クライアントは280を越える。以下を参照。
http://www.ingenta.com/corporate/company/clients/publ_customers.htm
また、Publishing Communication Group は関連会社でもあり、ジャーナル公開から、販売促進という面まで、一貫したサービスを受けることも可能。
以下は、昨年12月の SPARC Japan セミナーの講演。
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/2008/pdf/121608/4_Louise_SPARC%20Japan_Dec2008_v2-1.pdf
4. テラパブ
自社開発のプラットフォーム。学術情報流通の現場で、長く、日本の学会出版を支える会社。日本地球惑星科学連合の関連学会を軸に、理数系学会の欧文学会誌の出版および Online Monograph を Open Access で公開している。
http://www.terrapub.co.jp/
● 電子投稿査読システム
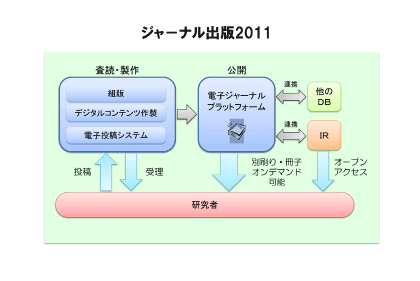
図3: 2011年のジャーナル製作
電子投稿システムはもはや、電子ジャーナル出版においては、欠くことができないものとなった。かつてのような高額な導入費は、すでに必要ではない。現状では初期費用としても十分支払い可能な金額となったと考える。またユーザーである研究者はすでに、海外誌への自らの論文投稿で、システムそのものをよく理解されておられるようになった。ただし、すでに時代は次世代へ移行しており、査読システムとコンテンツの製作過程は、一体化する傾向にある。海外印刷会社は、査読システムを出版フローに組み込み、ジャーナルを製作する(XML 化やレファレンス確認、タグ付け、DOI 付与等々を含めて)というフローでの見積書を出してくるようになっている。以下に記した数字は、年間使用料も含め、各社のHPに料金が記載されているものや、もしくは、実際にシステムを使用している学会等の情報により、その金額を記した。
上記の投稿・査読から出版、購読、DB 連携までのフローを図3に示す。
1. Editorial Manager®
Aries Systems が提供する電子査読システム。Aries Systems は1986年に設立。Editorial Manager® は3,000を越える出版物の査読システムとして採用されているが、その多くは、Elsevier、Springer のジャーナルであり、学会が単独採用を行っている数は著者は把握できていない。Editorial Manager® はすでに、eXtyle® をパートナーに迎え、査読→電子コンテンツ作成→プラットフォーム公開といった一連の業務をパッケージ化している。なお、eXtyles® 、eXstyles® を持つ Inera は2007年に SPARC Japan で以下の講演を行っており、当時より XML の重要性、また編集フローの中での業務の自動化は説明されていた。
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/backnumber/2007/pdf/02NII_SPARC_JAPAN_2007_Rosenblum.pdf
2. ScholarOne Manuscripts
杏林舎が日本代理店。2006年8月31日、Thomson Reuters の傘下に入る。杏林舎は、投稿規模が比較的少ない学会に対しても、支払額を抑えたモデルを提供している。初期費用は40万円ほど。年間使用料は、「投稿された論文数」による。これは他のシステムもほぼ同様である。すでに、多くの学会の要望を吸収、常に進化し続けてきたシステムだけに、安定感、利便性に富む。投稿論文数の増加、海外からの投稿の増加、rejection rate の上昇などを勘案すると、システム使用料としての100万円は高額ではない(年間350論文、為替レート1ドル90円)。
3. acPartner
IPAP(物理系刊行協会)が SPARC Japan の支援を受け、ダイナコム株式会社と開発した査読システム。投稿数に依拠しないモデルはユニーク。
モデル1 |
|
初期費用 3,150,000円 月額 52,500円 |
モデル2 |
|
初期費用 2,520,000円 月額(1-3年目)
73,500円(4年目以降)52,500円など初期費用とその後の月額費用とのバランスを計算したモデルである。支払い額等は相談に応じるとのこと。 |
現在、日本物理学会、応用物理学会で使用。
4. eJournalPress
ベセスタに本社を置く、Nature、PNAS を顧客に持つシステム。シンプルで、明解なシステムは、レッドアローの目印で、「自分が次ぎに何をすべきかを知らせる」CEO である Joel Plotkin、前職は NIH で、内分泌に関わるデータベース作成に当たっていた。現在、年間250論文以上を受け付けるジャーナルとそれ以下のジャーナルの2つのモデルを提供している。
250論文以上の場合は初期費用は$5,000、1論文につき$25の使用料、250論文以下の場合は、初期費用は$2,000、1論文につき$25の使用料となっている。100論文以下のジャーナルであれば、初期費用も含め、1年目は50万円前後で、このシステムが使用できる。ただし、ベセスタと日本は13時間の時差があり、投稿システムの日本での代理店はない。
● おわりにかえて
電子ジャーナルによる学術情報流通世界の拡大によって、研究者、図書館、学会、また学術政策に関わる様々な政府関係委員会や科研費を扱う独立法人、そして、まさに文部科学省、国までもが、恐らく、常にさまざまな「次」を考え、動き続けなければならなくなった。そういった意識を我々は皆で共有しているだろうか。いや、それ以前に、持っているだろうか。我々が立つ世界は「新しい何かを作れば、それで最先端に立てる」のではなく、「新しい何かはその瞬間に古くなる」のではないか。加えて、デジタルそのものが社会や実際の生活に与えている影響力は、活版印刷の発明を大きく超えるような衝撃を伴ってやって来たと言える。学術情報のデジタル化と簡単に書くことはできるが、これほど手に負えないものはないというのが、筆者の実感である。
一方で、日本の学術誌出版を長く支援してきた、科学研究費補助金研究成果公開促進費学術定期刊行物(以後科研費)に対する改革案が、平成23年10月より、学術審議会で審議されている。2 この科研費は、昭和22年終戦後の日本で、学術情報基盤の根幹である学術誌出版を支援すべく開始され、昭和40年から、科研費枠に入り、現在に至っている。
本稿で述べてきたように、学術誌出版そのものの在り方は根底から変化してきている。現在の補助項目対象である、直接出版費、英文校閲費、海外査読者への論文往復郵送費という3つの枠を外した、費用選択自由度の高い科研費補助を学会と言う立場からは望みたい。一方で、Open Access 誌スタートアップ支援も改革案に盛り込まれた。有力海外学会ジャーナル、大手出版社から、新刊 OA ジャーナルが刊行される現状を踏まえた3 重要な改革案である。つまり、今回の改革案は、長く続いて来た「出版補助的支援的性格」から「学術情報流通の今後の一つの方向性を国レベルで示す」という極めて異例の改革である。学術審議会がどのような方向性を示すのか、今後の動向を注目したい。
新しいビジネスモデル、Open Access、それらは、将来的にもっとも良い方法なのか、学術情報流通に関わる皆が、模索をしている。つまり、我々は今後も先鋭な、時代を切り開くシステムをすべて理解しないまでも、追いつく努力をも続けねばならない。なぜなら、情報がデジタル化することで、技術の革新が学術情報流通に大きな影響を与えてしまうことになったからだ。そして、学術情報世界は、著者 ID の世界レベルでの標準化により、また異なった様相を見せることになるだろう。最後に、2007年に出版された書籍から、以下の一文を引用させて頂く。
The technology has advances much more quickly than has our understanding of its present and potential uses.4
参考文献
| 1. |
Multi-Product Platforms: The Twenty-First Century Solution to Changing Demands upon Academic Publishers.
http://www.atypon.com/news/article.php?id=1120(参照2011-10-21) |
| 2. |
研究環境基盤部会学術情報作業部会(第44回)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/002-1/siryo/1311985.htm(参照2011-10-30) |
| 3. |
科学技術動向. http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt125j/menu.pdf(参照2011-10-31) |
| 4. |
Christine L. Borgman Scholarship in the Digital Age: information, infrastructure, and the Internet. The MIT Press, 2007, p. 3 |
|

