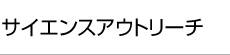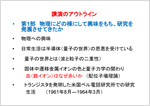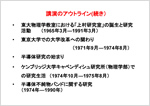出張授業
東京都立戸山高等学校
「物理学(特に量子物理)と日常生活・社会との関わり」
平成23年1月29日(水)
- 授業時間
- 14:00-16:30
150分×1コマ
出張授業担当者:
- 上村 洸(アドバイザー・東京理科大学)

授業担当者の感想
SSH戸山高校公開講座での講演
母校の公開講座では、SSH生(1,2年)、保護者、同窓生、都民、教員という聴衆の層の広さと、年齢分布がSSH生の15歳から筆者と同期のシニア世代まで広範囲であるために、講演の構想作りに苦労しました。最初にSSH生向けに、「物理にどの様にして興味をもち、研究を発展させてきたか」との話をし、次に「物理学と社会との関わり」、最後に、筆者が所属の「東京理科大における教育と研究」の3部に分けて話をしました。
ここではSSH生向けの話に絞って報告します。「毎日空を眺めて、空が何故青いかと考えたことがありますか」という問いかけから、自然科学では好奇心が重要との趣旨の講演を始めました。我々の日常生活が快適になるように、科学者やエンジニアが好奇心と英知を結集し、どのようにして半導体から素晴らしいデバイスを作成しているかのスライド(浜松フォトニクス作成)を見せながら、このようなデバイスを作るのには、「量子の世界」の物理をしっかり勉強することが重要との話をしました。「量子の世界」で、量子力学がどのようにして誕生したかの説明で、アインシュタインの光量子仮説とルイ・ドゥブロイの「電子は波」の二つを例にとって話をしたところ、SSH2年物理コースの生徒から、数々の質問があり、その質疑のやり取りから、会場全体が盛り上がって、講演の目的を達成することができました。講演後、SSH生から質問や相談が多数あり、大変実りの多い公開講座となりました。写真は、その時SSH生と一緒に撮ったものです(左端は、東京大学ポスドク笹岡健二博士)。また後日、上記SSH2年生から、「大学では物理学を勉強したい」との嬉しい礼状を頂き、感激した次第です。
[アドバイザー 上村洸]