永井 裕子(ながい ゆうこ/社団法人 日本動物学会 事務局長・UniBio Press代表/筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 博士後期課程)
● はじめに
UniBio Press は国立情報学研究所(NII)の事業活動のひとつであるSPARC Japanの支援を受け、複数の生物系学協会によって設立されたNPO法人である。また、UniBio Pressは、それぞれの学協会が独自に出版するジャーナルを海外図書館へはBioOne.2コレクションの参加ジャーナルとして、1) 国内図書館へは「UniBio Press」として、電子ジャーナルパッケージ購読を実現させた我が国で、唯一の団体でもある。UniBio Pressは、2004年設立時は、日本哺乳動物卵子学会、日本哺乳類学会、社団法人日本動物学会の3学会であったが、その後、日本爬虫両棲類学会、日本鳥学会、日本古生物学会が参画、現在、参画学会は6学会になった。
ここでは、UniBio Pressの7年間を辿りながら、連携協調を行っているBioOneについても、UniBioの活動をご理解いただくために、その簡単な歴史と現況について記述する。併せて、UniBioが海外プラットフォームから発信を続けながらも、商業出版社とは異なる立場にあるBioOneの方針によって知ることができたUniBio Press参画ジャーナルの海外での状況について報告したいと考える。2011年5月1日現在、UniBio Pressに参画する学会及びジャーナル名は以下の通りである。
日本爬虫両棲類学会 Current Herpetology http://zoo.zool.kyoto-u.ac.jp/herp/indexj.html
日本哺乳類学会 Mammal Study http://www.mammalogy.jp/japanese/
日本哺乳動物卵子学会 Journal of Mammalian Ova Research http://jsmor.kenkyuukai.jp/about/
日本古生物学会 Paleontological Research http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/
日本鳥学会 Ornithological Science http://wwwsoc.nii.ac.jp/osj/japanese/home.html
社団法人 日本動物学会 Zoological Science http://www.zoology.or.jp/
● BioOneについて
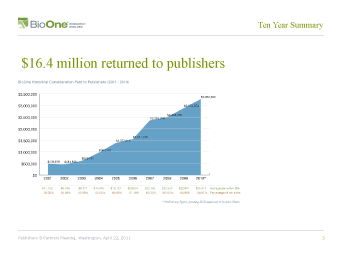
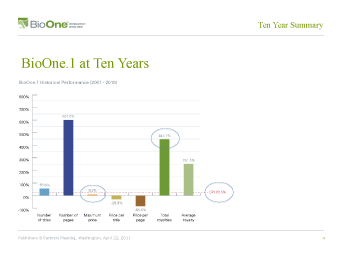
図1: COO Susan Skomal の講演から抜粋した資料
BioOneは、1999年、the American Institute of Biological Sciences (AIBS), SPARC (the Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition), The University of Kansas, Greater Western Library Alliance (前 Big 12 Plus Libraries Consortium)そして Allen Press, Inc.により、設立された。つまり、「学会連合」「図書館コンソーシア」「大学」「米国SPARC」と「出版社」が共に学術情報流通の未来を見据えて、生物系ジャーナルの新しいモデルを創出すべく、それぞれが、資金を出し合い、非営利組織として誕生した。2001年から、活動が開始され、2011年の今年は10年を迎えた。現在も理事会にあたるBoard of Directionsは、上記の出版社を除く4つの組織から、選出されている。一方で、Advisory Councilには、出版社から代表が1名入り、学会、図書館から代表者が出ている。2)図1は、2011年4月21日、ワシントンD.C.で開催された2011 BioOne MeetingにおけるCOO Susan Skomalの講演から抜粋した資料である。
BioOneのビジネスモデルは、世界に類を見ない。それは、購読料の半分をBioOneが経費として受け取り、半分は、ジャーナルのページ数とアクセスを用いた数式によって、各学会へ配分される。その金額は、明らかで正確なものである。従って、学会は、BioOneの中での自らのパーフォーマンスによって返還される「購読料」を受け取ることになり、なぜこの金額なのかという不透明な部分を抱えない。また、毎年の購読数の成長率なども報告されるので、返還金の増加を正しく把握することができると言える。
BioOneは、そのプラットフォーム使用料を含め、XMLフォーマットの統一といった経費も、BioOneで支払を行っている。ただし、生のログや、世界各国のコンソーシアへの「販売価格」などは、明らかにはされない。
2010 BioOne Publisher Reportによれば、2010年の購読状況は下記のようだった。
「世界における販売額は、2009年に比べ、15.4%上昇し、$4,360,603から$5,029,809となった。BioOne.1は1,339の図書館、研究所等の購読を受け、これは2009年に比べ、10.9%の増加だった。BioOne.2(UniBioが含まれる。)は714の購読数となった。特筆すべき点は、BioOne参加学会は、販売額の増加を年間購読料の上昇なしに獲得したということである」また「BioOne サイトは、24,972,873のアクセスを受けたとし、その中の10,384,724は、研究者による抄録と全文テキスト論文へのものだった。しかし、この数字、つまり“royalty-eligible” hits(ロイヤルテイを分配するに当たって、有効とするヒット-筆者訳)はCOUNTER 3を装備した影響で、2009年に比べ、10%減少した」。3)
● UniBio Press 国内図書館購読
UniBio Pressは、2004年電子ジャーナルサイトライセンシングを目指して、国立大学図書館協会(JANUL)4)との交渉の場を日本の学会としてははじめて持った。図2は、UniBioの代理店の変遷を示す。また、私が知る限りの商業出版社等の合併などを示す。ここからは、UniBioが電子ジャーナル販売を自ら行うことへの厳しさとその背景にある、めまぐるしいまでの学術情報流通の変動を垣間見ることができる。BioOneは、2007年から2010年まで、BioOneプラットフォームを使用したUniBio Pressパッケージ単独購読を「日本の大学図書館」にのみ提供した。2011年からは、UniBio Press の6誌は、BioOne.2に参加をしつつ、一方で「UniBio Press」として、日本国内図書館にUniBioジャーナル販売を再び開始することとなった。使用するプラットフォームは、2011年のみ、NIIのWEKO5)から、2012 年からは、サンメディアが提供するPierOnline6)からコンテンツを発信する。
UniBio PressはZoological Scienceを除いて、ジャーナル規模としては、けして大きいジャーナル群とは言えない。しかしながら、それぞれ、日本の「鳥類学」「古生物学」「爬虫両棲類学」「哺乳類学」を支える研究者が集う学会が出版を行っている。それらは、多くの学会同様、日本においてのみならず、海外においてもなくてはならないものである。
| 年 |
プラットフォーム |
ベンダー |
背景 |
商業出版界の動向(日付は発表日) |
| 2005 |
J-STAGE |
UniBio Press |
|
|
| 2006 |
・8/31 Thomson ReutersがScholarOneを買収
・11/17 WileyがBlackwellを1300億円で買収
・12/15 CIG*1がProQuestを買収 |
| 2007 |
BioOne |
CSA*2 |
BioOneと連携
BioOne.2パッケージ中の国内向け
UniBio単体販売開始 |
|
|
2008 |
ProQuest |
CSAとProQuest新会社設立 |
・10/7 SpringerがBMC*3を買収 |
| 2009 |
PCG*4 |
|
|
| 2010 |
|
|
| 2011 |
WEKO(NII) |
UniBio Press |
BioOne.2パッケージ中の単体販売終了に伴い、新プラットフォームへ移築 |
|
図2: UniBio Pressパッケージのプラットフォーム・ベンダーの変遷*1 Cambridge Information Group
*2 Cambridge Scientific Abstracts
*3 BioMed Central
*4 Publishers Communication Group
● BioOne.2 海外図書館購読
BioOne.2は先駆けて誕生したBioOne.1に比べて、販売額(年間購読料)も、小さく、購読館数も少ない。新しいパッケージであるということで、2010年は35%の伸びを示したが、次年度以降の購読料の状況は、不確かである。ここではBioOne Reportの中で、各学会に提供されるようになった、それぞれのジャーナルがどの組織からもっともアクセスを受けているかを一覧表にして附す(図3)。この表からは、各々のジャーナルのアクセス数を削除している。
図3: UniBio Pressがアクセスを受ける組織

/Zoological Science |
 |
/Current Herpetology |
 |
/Ornithological Science |
2009 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
COPPUL |
Canada |
2 |
NorthEast Research Libraries |
US |
3 |
Greater Western Library Alliance |
US |
4 |
SOLINET |
US |
5 |
CAPES |
Brazil |
6 |
University of Tokyo |
Japan |
7 |
Hokkaido University |
Japan |
8 |
Ontario Council of Universities Libraries |
Canada |
9 |
Knowledge Exchange-Germany |
Germany |
10 |
Kyoto University |
Japan |
|
|
2009 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
CAPES |
Brazil |
2 |
Knowledge Exchange -Germany |
Germany |
3 |
Kyoto University |
Japan |
4 |
Greater Western Library Alliance |
US |
5 |
Nylink |
US |
6 |
Unicersidade de Sao Paulo |
Brazil |
7 |
Fedlink |
US |
8 |
Unicersidade Federal do Rio Grande do Sul |
Brazil |
9 |
NorthEast Research Libraries |
US |
10 |
Johann Wolfgang Goethe University |
Germany |
|
|
2009 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
Greater Western Library Alliance |
US |
2 |
COPPUL |
Canada |
3 |
SOLINET |
US |
4 |
NorthEast Research Libraries |
US |
5 |
Nylink |
US |
6 |
CAPES |
Brazil |
7 |
Fedlink |
US |
8 |
Knowledge Exchange-Germany |
Germany |
9 |
RIKEN |
Japan |
10 |
Ontario Council of University Lib. |
Canada |
|
2010 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
UniBio |
Japan |
2 |
Knowledge Exchange |
Europe |
3 |
Greater Western Library Alliance |
US |
4 |
NorthEast Research Libraries |
US |
5 |
COPPUL |
Canada |
6 |
LYRASIS |
US |
7 |
Hokkaido University |
Japan |
8 |
Society Memebr Access |
Japan |
9 |
University of Tokyo |
Japan |
10 |
SOLINET |
US |
|
|
2010 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
UniBio |
Japan |
2 |
Knowledge Exchange |
Europe |
3 |
Aarhus University |
Denmark |
4 |
Greater Western Library Alliance |
US |
5 |
Kyoto University |
Japan |
6 |
HINARI, AGORA, and OARE |
Multi |
7 |
Copenhagen University |
Denmark |
8 |
NorthEast Research Libraries |
US |
9 |
Federal Library &Information Center |
US |
10 |
California Digital Library |
US |
|
|
2010 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
HINARI, AGORA, and OARE |
Multi |
2 |
Knowledge Exchange |
Europe |
3 |
UniBio |
Japan |
4 |
Greater Western Library Alliance |
US |
5 |
NorthEast Research Libraries |
US |
6 |
COPPUL |
Canada |
7 |
Fedlink |
US |
8 |
LYRASIS |
US |
9 |
CAUL |
Australia |
10 |
SOLINET |
US |
|
|
| /Paleontological Research |
 |
Journal of Mammalian Ova Research |
 |
/Mammal Study |
2009 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
Universidad de Buenos Aires |
Argentina |
2 |
Greater Western Library Alliance |
US |
3 |
University of Tokyo |
Japan |
4 |
NorthEast Research Libraries |
US |
5 |
COPPUL |
Canada |
6 |
CAPES |
Brazil |
7 |
Knowledge Exchange-Netherland |
Netherland |
8 |
Knowledge Exchange-Germany |
Germany |
9 |
Knowledge Exchange-UK |
UK |
10 |
Kyoto University |
Japan |
|
|
2009 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
Tokyo University of Agriculture |
Japan |
2 |
SOLINET |
US |
3 |
University of Tokyo |
Jaoan |
4 |
Chinese Academy of Sciences |
China |
5 |
RIKEN |
Japan |
6 |
Tohoku University |
Japan |
7 |
Rakuno Gakuen University Library |
Japan |
8 |
NorthEast Research Libraries |
Japan |
9 |
Knowledge Exchange-Germany |
Germany |
10 |
Nylink |
US |
|
|
2009 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
HINARI, AGORA,and OARE |
Multi |
2 |
Hokkaido University |
Japan |
3 |
Kyoto University |
Japan |
4 |
COPPUL |
Canada |
5 |
Fedlink |
US |
6 |
Forestry and Fisheries Research Council |
US |
7 |
University of Tokyo |
Japan |
8 |
Greater Western Library Alliance |
US |
9 |
Nylink |
US |
10 |
Knowledge Exchange-Germany |
Germany |
|
2010 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
Knowledge Exchange |
Europe |
2 |
UniBio |
Japan |
3 |
Greater Western Library Alliance |
US |
4 |
Society Member Access |
Japan |
5 |
NorthEast Research Libraries |
US |
6 |
COPPUL |
Canada |
7 |
LYRASIS |
US |
8 |
University of Tokyo |
Japan |
9 |
CAPES |
Brazil |
10 |
Universidad de Buenos Aires |
Argentina |
|
|
2010 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
UniBio |
Japan |
2 |
University of Tokyo |
Japan |
3 |
Knowledge Exchange |
Europe |
4 |
Tokyo University of Agriculture |
Japan |
5 |
RIKEN |
Japan |
6 |
Kyoto University |
Japan |
7 |
Osaka University |
Japan |
8 |
Veritas University |
Nigeria |
9 |
eIFL |
Multi |
10 |
Shinshu University |
Japan |
*大阪、信州大学はUniBio 購読館。区分けの方法は
*不明 |
|
2010 |
| Rank |
Institution/Consortium |
Country |
1 |
UniBio |
Japan |
2 |
Knowledge Exchange |
Europe |
3 |
Society Member Access |
Japan |
4 |
Iwate University |
Japan |
5 |
Hokkaido Universuty |
Japan |
6 |
Universitaet Bonn |
Germany |
7 |
ULB Bonn |
Germany |
8 |
*下記 |
Germany |
9 |
Greater Western Library Alliance |
US |
10 |
HINARI, AGORA,and OARE |
Multi |
*Bibliothek des Zoologischen
*Forschungsmuseum Alexander Koenig |

● UniBio Pressビジネスモデル
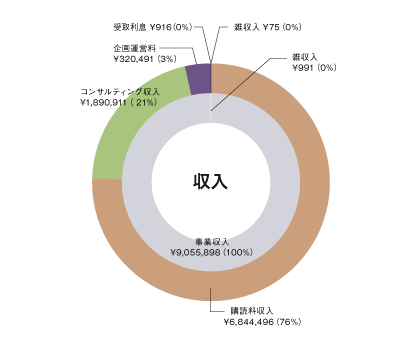
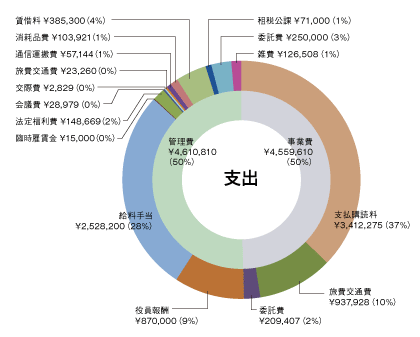
図4: UniBio Pressの2010年決算の概略
UniBio Pressの2010年決算の概略を、図4にお示しする。
UniBioの最大の、そして実際的な使命は、「電子ジャーナル購読による購読料を正当に、そして最大限に参加学会に返還する」ということであった。ここには、そのことで、そのジャーナルの地位を高めたり、名を広めたりという目的があることも確かである。また、UniBioに参加当時はImpact Factor (IF)を持たなかった、日本古生物学会Paleontological Researchが2009年から、日本哺乳類学会Mammal Studyと日本鳥学会Ornithological Scienceが2010年から、Web of Scienceに収録された。
UniBioの活動を支えるためには、実際には、そのための費用が必要となる。UniBio Pressでは、昨年はBioOne Reportにしめされた各学会の返還額をそのまま、学会に返還している。これは、「明確な数字」で学会に購読料を戻したいという理由による。その一方で、国内販売額とその年によって、返還があるかないかわからないのであるが、BioOneのいうSurplus Share paymentsの合計で、人件費と活動費、事務所賃貸料や会計監査料をUniBio Pressは支払っている。UniBio Pressの理事会では、UniBioは、BioOneからの購読料から、もっと収入を取り、人件費を上げるべきであるという意見が出ているが、代表である筆者は、学会への購読料返還を増加させることのほうが急務であると考えている。また、2011年4月にBioOneから返還された額は、$62,947である。この金額は、UniBioがBioOneと連携協調を始めた2007年の時点で、1クール3年の契約が終了する2010年の段階で、目標としていた金額であった。しかしながら、円高という状況が展開する中、円建てでは実質240万円に近い金額を失うという、UniBioにとっては大きな打撃を受けることとなった。
● 日本の生物系ジャーナル
UniBio Pressが、なぜ6学会の参加学会しか集められないのだと、質問を受けることがある。UniBio Pressのこの7年間の経験から、ここでは、その問題に回答する責任が筆者にはあると思う。これは、UniBioの活動が研究者の方々になかなか理解されないという問題から、生物系学会が現在抱える大きな問題をも含むものである。生物は細分化した分野が多く、特に我が国では、個々の学会規模は大きくはない。そのため、ジャーナル出版を行う際には、商業出版社に広告をはじめ、販売を委託することが、ジャーナルのために良いという考え方も強く、これはまた大変正当な意見である。またNature, Scienceをトップとしたジャーナルランクも強固であり、近年はここに、BMC7)やPloS8)といったOpen Access(OA)モデルを基本とした、しかもIFが高いジャーナルを抱える、生物学者にとっては、新たな投稿先も登場している。その上に、生物は爆発的とも言えるほど、研究成果が出続けてもいる。一旦、商業出版社による洗練された出版フローに慣れた学会は、ひとつのたとえとしてであるが「UniBio のような、またはBioOneのような、学会出版を支えるために努力をしたい。図書館の苦しい財政状況を助けたい」といった考えを持つ非営利団体よりは、「研究者が誰でも知っている」という場での出版を望んでいるように、私は実感している。それは以下の経験によるものである。商業出版社から出版を続けている学会2つから、UniBioと商業出版社を比較検討するという申し出を受け、UniBioは、投稿査読システムのアドミン料金までを含め、割安感のある提案を行った。だが、結果は商業出版社での出版継続であった。商業出版社が、次期の契約をさらに安価なものにしたのかどうかは、別としても、研究者には、商業出版社でのサイトにジャーナルが載っているという安心感が重要なのだと、学会からの説明を聞いた。また、商業出版社での委託は開始してはいないが、次のステップを踏むために、UniBioと商業出版社を比較検討した学会も2つあった。このうちの一つの学会は商業出版社での委託に踏み切った。若い研究者の方々の希望が強く、自らのジャーナルの地位向上や、認知度を上げるためには商業出版社だという意見が多く出たと聞いた。もうひとつは、現状のままの出版をOAで続けていると聞く。この学会ではOAであることを重要視しているように思われた。これらの4つの学会ジャーナルはすべてIFを持つ、我が国を代表する良いジャーナルであることをここに書かせていただきたい。「図書館が高い購読料を支払うことができず、その上で、毎年値上げに苦しんでいる」「日本の税金を使って出した成果を読むために、海外出版社パッケージをまた日本の税金を使って購読している」といった現況は、研究者の、または学会にとっての「ジャーナル出版を維持するためや、そのジャーナルの地位を上げるため、商業出版社に出版を委託する」時の、検討課題にはならない。研究者の多くが、電子ジャーナル購読料が大変高価であると理解していてもである。わが国は、拙稿で書いたように、IFの高いジャーナルへの論文掲載が、研究資金獲得では大きなポイントを稼ぐ。9)この頃では、特に若い研究者の方々が、よりIFを重要視しているとも聞く。そのことは、研究者による商業出版社への強固な信頼へとつながるのだろう。これは、「ブランド力」と言い換えても良い。BioOneにブランド力がないとは筆者は考えていないが、研究者にとっては、特に日本の研究者にとっては、ほとんど馴染みのないものと言ってよいと考える。
UniBio Pressの活動を続けてきたこの数年間は、UniBioのみならず、学術情報流通世界に関わる者にとって、大変厳しい時代であった。急速なOpen Accessへの動きがその一つである。OAは重要な方向性ではあり、学会は、商業出版は、それを放置しておくわけには、もはやいかない時代である。しかし、そこには、必ず「資金をやりくりする計算」が伴う。そこをなくしての、理想論、もしくは感情論、または待望論のようなOpen Access論はさすがに影を潜めたと思いたい。すでに、BMCやPloSの台頭に象徴されるように、OAモデルは確実に浸透している。当初の多くの批判や不安定さを払拭し、リスクを抱えても、彼らはその地位をすでに獲得している。「投稿料約25万円」を支払っても、論文をBMCやPloSで出版したいと考えている研究者も多いようだ。ここには、図書館の苦しみはない。値上がりする購読料はもはや存在しないからだ。しかし、同時にここには図書館の介在もなくなっている。
● これからの学術情報流通世界  ─ 終わりにかえて ─ 終わりにかえて
ジャーナルは今後も存続するのだろうか。すでにElsevierは、次の段階へのひとつの方向性を示した。10)この方向性の背景には、我々の想像を超えた技術の進展がある。かつて、ジャーナルは、ひとまとまりの巻と号に「規定」されていた。しかし、それが解体する、もしくは意味をなさないことになるのは、目前に迫っているように思える。個々の論文のパーフォーマンスは、アクセス数、引用数を示すことで可能である。アクセス数を評価することには慎重な検討が続いているが、引用数は、重要な評価基準の一つだ。それは、雑誌のパーフォーマンスを示すIFより、実際的な数字なのである。しかも、個々の論文はDOIですでに識別されている。論文単位評価の環境は整ったと言える。出版を行う学会としては、「品質保証」としての査読を引き受けたいが、それも、かつてNatureが行ったように、Openになってしまうのだろうか。11)また、Big Dealモデル12)に図書館がいつまで耐えうるのか、それも大きな焦点だ。「必要なジャーナルだけを購入する」もしくは「読んだ論文だけの支払いを行う」といったモデルが進めば、選ばれないジャーナル、読まれないジャーナルが明確になる可能性もある。学会は、ぜひとも選ばれる側のジャーナルでありたいが、それは研究者が「質」で選ぶことになる。
最終的には、宇宙のような空間、それをクラウドと言っても良いかもしれないが、そこには個々の論文がDOIを付与されて分野別にあるということなのだろう。もちろんOpen Accessであり、研究者は、そこに自らの論文を登録し、また登録される論文から、質を見極め、引用を行う。読みたい研究者の論文が登録されれば、そのalertが来る。これは遠い世界の話ではなく、すでに、ほとんどが、我々の手に入っているものだ。しかし、学術情報世界全体が、わけても研究者が当たり前の学術情報の「出版」手続きとして、上記のような世界を認めていくには時間が必要である。また「査読による品質保証」をどうしていくのか、それも大きな課題だろう。そして、実際には、それまでどう我々が、ジャーナル出版を行うのか、なにがもっとも適した在り方なのか、2011年の今、学会出版の一員としておおいに悩むところである。
UniBio Pressは国の支援を受け、生物系ジャーナルとしては、日本において、いままでにないあり方を、模索し続けている。しかしながら、この7年間、UniBio Press、BioOneの在り方が、「必ず正しい、一番良いということではない」と常に参加学会の方々に筆者は言い続けてきた。それは、めまぐるしい学術情報世界にあって「これが王様である」といった方法は存在しないからだ。有力ジャーナルがその質はもちろん、さまざまな方法で自らの地位を高めようとしのぎを削っている今、電子ジャーナルコンテンツをどこかのサイトで出版していれば良いということではジャーナルの地位を高められないという考えには多くの方がご理解をくださるだろう。冊子を出版している時代は、平和でのどかな時代だった。その時代と電子ジャーナルの発行を同じに考えてはならない。この時代にあっては、むしろ、どういったプラットホームで、電子ジャーナルコンテンツをどうやって発信していくか、そして、そこから得られる様々な情報を次にどう活かしていくのかということが、質の維持、そのジャーナルが重要視する論文の選択と共に、需要なことなのではないかと考えている。皆様はどのようにお考えだろうか。
次回へ続く
※ 注 釈・参考文献
|

