|
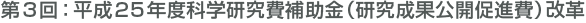
近藤 英夫(こんどう ひでお)
東海大学文学部
私は、インド・パキスタンの考古学の研究者である。現在は、日本考古学協会に所属しており、同協会の理事を務めている。文科省の科学研究費補助金(研究成果公開促進費)が大きくそのかたちを変えることを聞いて、その内容を詳細に知りたく、2012年7月25日(水)に開催された第3回 SPARC Japan セミナー「平成25年度 科学研究費補助金(研究成果公開促進費)改革」ワークショップに参加した。
当日のプログラムは、「学術定期刊行物助成制度(略)改革の方向性について」小山内優氏(日本学術振興会)/学会ジャーナルのプロモーション活動:報告とこれから」山下和子氏(化学工学会)/「科学基礎論学会における欧文誌刊行の現状と問題点」菊池誠氏(科学基礎論学会)/質疑、であった
小山内氏が述べた助成制度の「改革」というのは、「紙媒体による情報発信から、電子データによる国際的情報発信へ」の転換ということである。今後は、いかに「国際情報発信強化」をしているか、ということが評価の対象になるという。具体的には、オープンアクセスを前提とした電子ジャーナル(E-journal)の刊行である。この改革は、今年度の科研費公募から適応されるという。
小山内氏に続いて、山下氏・菊池氏の報告があった。両氏の報告は、「国際的な視野にたつことの大事さ」を基調とし、個別学会相互が連携をもつことの必要性、欧文誌を刊行することの重要性などを、強調していた。実体験から導きだされたその主張には、私も一研究者として同感するところであった。
セミナーに参加して感じたことを以下に述べる。
国際的視野にたって研究を押し進めること、海外の研究者と恊働する機会を、わが国の学会が率先して提供することは、これからの日本の学会にとって必要なことである。研究のガラパゴス化、個別細分化を忌避する方策は、とられてよい。
そういった意味で、筆者は、今回の助成制度の改革には「総論賛成」である。ただ、個別学会には「困ったことになったぞ」という声がでてくるな、という印象をもった。
私の所属する日本考古学協会は、人文系学会ではあるが、ドメステッィクな研究者ばかりではなく、欧米に接点をもっている研究者や、海外の遺跡発掘など共同調査をすすめている人も多くいる。さらには、数理分析的な研究を進めている研究者もいる。そういうこともあって、人文系学会の中では、E-journal 刊行への対応は比較的可能な環境である。社会系の学会も、多くは適応しやすい環境にあると言える。たとえば政治学や社会学、ジャーナリズム関係の学会などは、対応可能であろう。こうした学会については、今回の「改革」を、スムーズに発展的に受け入れることができるであろう。
その一方、いくつかの人文系の学会では、E-journal の刊行に不向きな学会もあるのではないかと思量する。たとえば、民俗学、国文学などは、今回の動きにどう対応するのかと心配になってくる。こうした学会の存在を思うと、「紙媒体」を評価対象に残すことはできなかったのかという気も、正直、している。
E-journal 刊行に関しては、確認しておきたいことがある。国際情報発信のツールとして、E-journal 刊行の必要性はわかるのであるが、フランスやドイツなどの非英語圏の電子ジャーナルの実態がどうであるかということが、気になるところである。セミナーでは、こうした国々が電子媒体をどう活用しているか、などの情報の提供があってもよかったと思う。
さらにセミナーに参加して気付いた点があったので、以下、述べる。助成制度の議論をする際、どうしても所属学会(私の場合は、日本考古学協会)がどう助成を受けるかということを基準に話しを聞く。それはしかたのないことであるが、セミナーに参加してみて、その学会単位の枠組みをバラして考えるということもあるのではないかと思い至った。
それは学会再編というようなことではない。複数の学会が主体性をもって呼びかけ、そして呼応し、E-journal を刊行するということである。その、E-Journal を仲立ちにして、複数学会が連携をして広領域をカバーする恊働研究をすすめることである。このためには、海外を対象にした恊働作業だけでなく、国内にも眼を向けて、新たな枠組みをつくる必要がある。人文系の学会が、隣接諸科学のみならず、理工系、生物系の学会と共通のテーマで議論ができたら、それは楽しいことのような気がする。ただ、具体的にはこの準備が短期間にできるのだろうかと、今年度は無理かなと思う次第である。
最後になるが、セミナーの議論を通して気になったことがあるので述べておきたい。それは、E-journal の必要性を説く際に、例として挙げられたのが “Science” “Nature” の2誌であったことである。この2誌の例示は、理工・生物系には適切なであるが、人文・社会学系はまた別な冊子を例として挙げなければならないであろう。それと、紙媒体の時代にすでに権威を確立している伝統的2誌を、新しく模索する E-journal の目標としておくことには、私は、抵抗を感ずる。

佐藤 翔(さとう しょう)
筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科
参加前、今回のセミナーはビジネスモデルの話題が中心になるものと思っていた。
オープンアクセス(OA)出版のビジネスモデルに関し、記憶に新しいのは2012年2月に開催された SPARC Japanセミナー「OA メガジャーナルの興隆」である。その中で講演者の Peter Binfield 氏は「2020年には世界の論文の90%は、PLoS ONE のような OA メガジャーナルに掲載される」と予想した。OA が購読出版のシェアを奪う未来が現実味を増して感じられる中での、研究助成機関自らが刊行する OA 誌、eLife 登場である。英国ウェルカム・トラストなど、各国最大手の助成機関が合同で、当面は論文出版加工料(APC)無料の OA 誌を創刊する。APC に助成するよりも自前で出版する方が低コストと判断したのか、あるいは採算度外視で購読誌の息の根を止めにかかったか。そういう話になることを期待していた。メインプレゼンターである eLife の Mark Patterson 氏の講演に先立っては、尾城孝一氏による開会の挨拶、市原瑞基氏による「オープンアクセス出版の動向」についての解説が行われたが、いずれもビジネスモデルが話題の中心で、自分と同様の期待を抱かれていたのではないかと思う。
しかし Patterson 氏の講演は予想を裏切るものであった。氏が OA を支持する根底にはかつて遺伝学研究者であった経験があるという。遺伝学におけるデータの共有はヒトゲノムプロジェクトに結実し、30万人分以上の雇用につながった。これぞ研究成果をオープンにすることの意義だ、と氏は語った。その背景ゆえに、氏が目指しているのは研究成果を単に無料で閲覧できることではない。それを「再利用」できるようにすることが目的なのだ、という。以降も Patterson 氏は繰り返し「再利用」を認めること、すなわちクリエイティブ・コモンズの CC-BY ライセンス(出典さえ明示すれば商用も含めた自由な再利用が可能)を採用し、研究成果を自由に使えることの重要性を強調した。当然、eLife は CC-BY を採用するし、研究の元データとも論文を関連付け、利用を促すという。講演ではその他にも現在の査読の問題点の改善等も eLife の目的であると述べられた一方、ビジネスモデルに関する話題はほとんどなかった。フロアとの質疑ではじめてビジネスモデルに大きく触れられたが、「持続可能性を実現する方策がはっきり見えているわけではない」「雑誌自身をパワフルにすることで…」と述べる程度であった。
その後のパネルディスカッションでは、斎藤博久氏より購読誌から OA 誌に転換した日本アレルギー学会の雑誌『Allergology International』について、小島陽介氏から来年度には OA 誌を6誌創刊するという出版社カルガーの動向について、内島秀樹氏より図書館から見た OA 誌への期待に関しての発表があった。その後に、パネリスト間の議論に入った。その議論でも Patterson 氏は「再利用」に強く拘り続けた。
予想と異なる内容に当初は肩透かしの感もあったが、「再利用」に関する Patterson 氏の熱意はよく伝わった。「再利用可能な未来」、素晴らしいではないか。
しかし当原稿のために昨今のOA関連の議論を見直すうち、そう単純な話ではないことに気付かされた。再利用可能性まで持った OA を libre OA、自由なアクセスは認めるが再利用可能性までは問わない OA を gratis OA というが、この差はこれまでそう大きくは取り沙汰されて来なかった。しかしここに来て OA に関する中心的な話題になっている。いずれのレベルまで求めるかが、機関リポジトリ等のセルフ・アーカイブ(いわゆる Green OA)と OA 出版(いわゆる Gold OA)のどちらを優先するかという、長年の論争と結びついているのである。現在、多くの出版社は購読誌掲載論文でも条件付きでセルフ・アーカイブを認めている。しかし商用まで含めた自由な再利用を認める例は少ない(認めてしまえば他社も自由にその論文を雑誌に載せたり、別刷りを販売できてしまう)。一方、APC による Gold OA であれば、出版時点でコスト回収は済んでいるはずで、論文を他社に利用されても問題がない(事実、PLoS 等の大手 OA 出版は CC-BY ライセンスの採用が多い)。Green OA では gratis OA までしか実現できず、libre OA を実現できるのは eLife のような Gold OA だけである。必然的に、libre OA を支持することは、Green ではなく Gold を支持することへとつながる。
実際に英国研究会議(RCUK)が最近、発表した OA 方針は libre OA を重視し、Green OA よりも Gold OA を優先する内容となっており、Green OA 支持者から反発を招いている。他方で、RCUK の方針は eLife をはじめとする Gold OA には後押しとなる。政府や助成機関が libre OA を義務付ければ、前述の通り CC-BY を採用しにくい購読誌から Gold OA に投稿が流れる可能性は大きい。
ビジネスモデルの確立と合わせ、いよいよ Gold OA が購読誌のシェアを奪うか、あるいは購読誌の Gold OA 化が進むか。eLife の振る舞いはそれらの状況にどう影響を与えるのか。そのとき Green OA はどうなるのか。ビジネスモデルの話ではなかったが、あるいはそれ以上に、今回扱われた「再利用」の可否は学術出版界の未来を左右するものと言える。創刊予定月を待たずして本稿執筆時点でeLifeの最初の論文は既に公開されているが、同誌および「再利用」をめぐる今後の動向には注目し続ける必要がある、そのことに気付かされたセミナーであった。
|

